
「湿気と湿度の違い」を知ることは、快適な暮らしを実現するために非常に大切です。
湿度とは、空気中に含まれる水蒸気の割合を示す数値で、湿気はその水分が物や空気に含まれて現れる状態や、カビや結露などの目に見える現象を指します。
この違いを理解することで、なぜ季節や天候によって室内の環境が変化するのかがよく分かります。
例えば、梅雨や夏の時期は湿度が高くなるため、部屋がジメジメして不快に感じたり、カビやダニが発生しやすくなったりします。
逆に冬は湿度が低くなりやすく、肌や喉の乾燥や静電気の発生といった不快感を引き起こすこともあります。
このように、湿気と湿度の違いを理解し、季節ごとに適切な湿度管理を行うことが、健康的で快適な住環境を保つためのポイントです。
湿度計を使って室内の湿度を確認し、40~60%を目指して湿度を調整することで、より快適に過ごすことができます。
まずは自宅の湿度をチェックし、今すぐできる湿度対策を始めてみませんか?
「湿気と湿度の違い」を理解することが、日々の暮らしを快適にする第一歩です。
▼その他の梅雨の湿度対策に関する記事はこちらをチェック▼
梅雨の湿度対策で快適な部屋づくり!部屋干しも安心のカビや臭いを防ぐテクニックまとめ
湿気と湿度の違いとは?

「湿気」と「湿度」、どちらもよく耳にする言葉ですが、実はその意味や使われ方には違いがあります。
普段の生活の中で「なんだかジメジメするな」と感じるとき、それは湿気なのか湿度なのか。
ここでは、それぞれの言葉の意味や特徴、そして使い分け方について、わかりやすく解説していきます。
湿気の定義と特徴
「湿気」とは、空気中や物の表面に含まれている水分のことを指します。
たとえば、梅雨の時期に部屋の空気がジトっと重く感じたり、窓ガラスが曇って水滴がついたりするのは湿気によるものです。
洗濯物がなかなか乾かないときや、押し入れにしまった服や本がしっとりしているときにも「湿気がこもってるな」と感じることがありますよね。
湿気は、数値で測るというよりも、実際の感覚や見た目で判断されるのが特徴です。
「ジメジメする」「ムシムシする」といった体感や、カビや結露などの目に見える現象としてあらわれることが多く、住環境に大きく影響します。
特に換気が不十分な場所や、気温と気圧の影響を受けやすい季節では、湿気を強く感じやすくなります。
こうした点からも、湿気は快適な暮らしを守るためにしっかり意識しておきたい要素です。
湿度の定義と種類(相対湿度・絶対湿度)
「湿度」とは、空気中に含まれる水蒸気の割合を示す数値のことです。
主にパーセント(%)で表され、「今、空気がどのくらい水分を含んでいるか」を数値で把握できます。
湿度には2つの種類があり、それが「相対湿度」と「絶対湿度」です。
相対湿度は、そのときの気温で空気が保持できる最大の水蒸気量に対して、実際にどれくらいの水分が含まれているかを割合で示したもの。
たとえば相対湿度が60%なら、その気温における水分の最大量のうち60%が含まれている状態です。
一方で、絶対湿度は空気1立方メートルあたりに含まれる水蒸気の質量(g/m³)を表しており、温度に関係なく水分量を把握できます。
湿度の数値を知ることで、カビ対策や結露防止、エアコンや加湿器の設定など、快適な室内環境づくりに役立ちます。
湿度の管理は体調管理にもつながるため、毎日の暮らしで意識しておきたいポイントのひとつです。
湿気と湿度の使い分け・体感の違い
湿気と湿度はどちらも空気中の水分に関わっていますが、それぞれ使い方や感じ方が異なります。
「湿気」は感覚的なもので、「部屋がジメジメする」「壁がしっとりしている」など、目に見えたり触ったりできるような状態を指すときに使われます。
反対に「湿度」は、湿気の状態を数値で表したものです。
「今日は湿度が高い」「湿度60%」といったように、湿度は明確なデータとして表現されます。
たとえば、湿度が高くなると空気中の水分が増えて、肌にべたつきを感じたり、洗濯物が乾きづらくなったりすることがありますが、その状態を体で感じるのが「湿気」、測定器で確認できるのが「湿度」です。
このように、湿気は日常の体感や生活の質に直結し、湿度はその原因や状況を知るための客観的な指標といえます。
両者を上手に理解して使い分けることで、より快適な住まいづくりや健康的な毎日をサポートするヒントになります。
温度と湿度の関係性
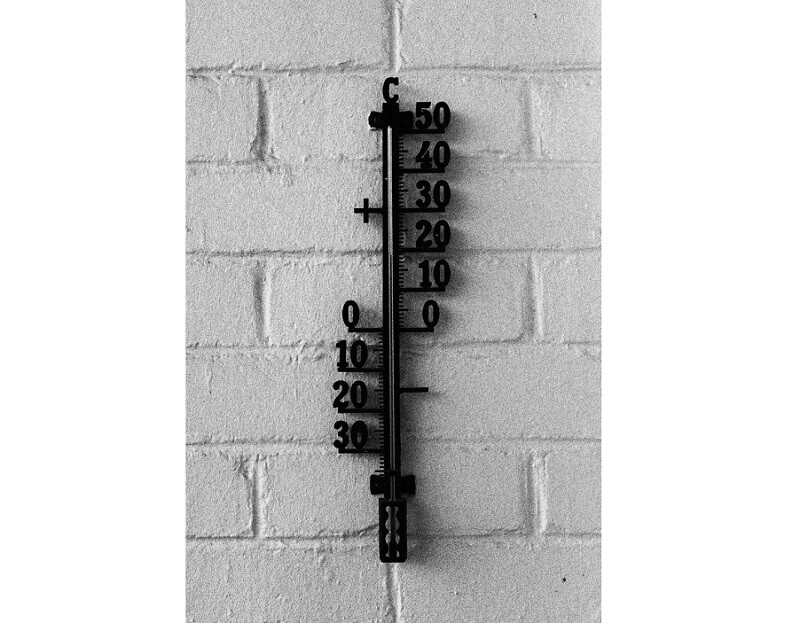
温度と湿度は、私たちの暮らしに欠かせない空気の要素です。
なんとなく「今日は蒸し暑い」「乾燥してるな」と感じるのも、実はこの2つのバランスが影響しています。
このセクションでは、温度が湿度にどう影響するのか、湿度が体感にどんな風に関わるのかを、日常の実例をまじえながらわかりやすく解説していきます。
温度による湿度の変化
温度と湿度は密接につながっていて、空気の温度が変わることで湿度も変化します。
具体的には、暖かい空気はたくさんの水分を含むことができるのに対し、冷たい空気は水分をあまり含めません。
気温が上がっているのに湿度が低く感じる日があるのは、空気が多くの水分を抱えられるようになって、相対的に湿度の数値が下がるためです。
反対に冬場は気温が低く、空気があまり水分を含めないので、少しの水分でも湿度が高く表示されることがあります。
冬の朝に窓にびっしり水滴がついているのを見たことがありませんか?
これは、夜間に気温が下がって空気中の水分が飽和し、余分な水分が結露として現れるためです。
こういった変化は、室内の快適さにも大きく関わっていて、湿度が高すぎるとカビの原因になったり、低すぎると乾燥による不快感を引き起こしたりすることもあります。
だからこそ、温度と湿度の関係を知っておくことは、快適な暮らしづくりにとても大切なのです。
体感温度と湿度の関係
気温が同じでも、「今日はやけに暑いな」「なんだか寒く感じる」と思うことはありませんか?
それは、湿度が大きく関係しているからです。
湿度が高いと、私たちの体から出た汗がうまく蒸発しにくくなります。
そのため、熱が体の外へ逃げにくくなって、実際の気温以上に暑く感じてしまうのです。
特に梅雨や真夏の蒸し暑さは、この湿度の影響によるものです。
逆に湿度が低いと、汗がすぐに蒸発して体温が下がりやすくなるため、同じ気温でも涼しく感じることがあります。
冬に空気が乾燥して「肌がカサカサする」「喉がイガイガする」と感じるのも、湿度が低くなる季節特有の現象です。
最近では、体感温度をより正確に表すための「不快指数」や「暑さ指数(WBGT)」といった指標も使われており、天気予報や熱中症対策の参考にもなっています。
日々の生活を快適に過ごすためには、温度だけでなく湿度にも注目することが大切です。
適切な湿度を意識することで、蒸し暑さや乾燥からくる不快感をやわらげやすくなります。
夏と冬で感じ方が違う理由
「夏の湿度60%はジメジメしてつらいのに、冬の60%はちょうどよく感じる」。
こんな風に、同じ湿度でも季節によって感じ方がまったく違うことがあります。
これは、空気が温度によってどれくらい水分を抱えられるかが変わるためです。
夏は空気が多くの水分を持てるので、湿度が高いと汗がうまく蒸発できず、蒸し暑さやベタつきが気になります。
一方で冬は、空気中の水分量がそもそも少なくなるため、同じ湿度でも乾燥がやわらぎ、快適に感じることが多いのです。
さらに、冷暖房の使用も湿度に影響します。
暖房を使うと室内の空気が乾燥しやすくなり、喉の不快感や肌の乾燥につながることがあります。
冷房の場合は逆に湿気を除去するので、除湿しすぎると肌寒く感じることも。
だからこそ、季節ごとに適切な湿度を保つ工夫が必要です。
加湿器や除湿機、サーキュレーターなどを上手に使えば、年間を通じて快適な空間を維持しやすくなります。
こうした湿度と体感の関係性については、気象庁や環境省などの公的機関でも紹介されています。
生活に取り入れやすい情報をもとに、季節ごとの快適対策を意識してみてください。
湿気がたまりやすい原因とその影響

湿気は目に見えないものですが、暮らしの快適さや住まいの状態に大きな影響を与えます。
特に梅雨や夏など湿度が高い季節になると、室内のジメジメが気になる方も多いのではないでしょうか。
この章では、湿気が多くなる時期や場所、さらにそれがどんなトラブルにつながりやすいのかをわかりやすくご紹介します。
天候や季節による湿気の違い
湿気は天候や季節の変化によって大きく変動します。
たとえば梅雨や夏は、気温が高くなるとともに空気中に含まれる水分量も増えるため、ジメジメとした不快感が強まりやすいです。
反対に冬は、気温が低いため空気が含める水分量が少なくなり、湿気が少なく感じられます。
春や秋は気温も湿度も安定しやすい時期ですが、急な寒暖差によって窓に結露ができやすくなることもあります。
気象庁のデータでも、季節による湿度の特徴が明確に示されています。
特に梅雨時期は湿度が80%を超えることも珍しくなく、放っておくとカビや結露が発生しやすくなります。
一方で冬は湿度が30%以下になることもあり、空気の乾燥が気になる季節です。
こうした特徴をあらかじめ知っておくことで、時期に合った湿気対策がしやすくなります。
季節ごとの湿度の違いを意識することが、快適な住まいづくりの第一歩です。
場所や住環境が与える影響
湿気がたまりやすいかどうかは、家の間取りや生活習慣によっても変わります。
窓が少ない部屋や、風通しが悪く換気しにくい場所は、湿気がこもりやすい傾向があります。
北向きの部屋や地下にある部屋も、日当たりが少なく乾きにくいため、湿度が上がりやすくなります。
また、浴室や脱衣所、室内干しをする部屋など、水分が多く関わる場所は自然と湿気が増えます。
観葉植物が多い空間や、水槽を置いている部屋なども要注意です。
さらに、寝室も見落としがちですが、人が長時間過ごすことで呼気や汗などの湿気が溜まりやすい場所とされています。
こうした場所では、定期的に窓を開けて空気の入れ替えをすることが基本です。
公的な住環境のガイドラインでも、湿気を溜め込まないために「換気と除湿のバランス」が大切だとされています。
自宅のどこが湿気をためやすいのかを把握することが、効果的な湿気対策のスタートになります。
湿気が引き起こすトラブル(カビ・結露など)
湿気が多い環境では、さまざまな困りごとが起きやすくなります。
特に代表的なのが、カビと結露です。
カビは湿度が60%以上の環境で発生しやすく、壁や家具、カーテン、洋服などに黒い斑点が現れることもあります。
放っておくと見た目の問題だけでなく、物の劣化にもつながってしまうことがあります。
また、結露も要注意です。
冬場に窓ガラスがびっしょり濡れているのを見たことはありませんか?
これは、室内の暖かい空気と外の冷たい空気の温度差によって、水分がガラスに集まってしまう現象です。
この水分がカビの原因になったり、木製の窓枠を痛めたりすることもあるため、こまめな対策が必要です。
さらに、湿気が多いと空気がなんとなく重たく感じたり、部屋全体がジメジメして不快になったりすることもあります。
こうした不快感は、日々の生活の質にも関わってきます。
気象庁や環境省なども湿度管理の重要性を発信しており、湿気対策は暮らしを守る大切なポイントといえるでしょう。
湿度と快適な生活環境の関係

湿度は、日々の暮らしを心地よく保つために欠かせないポイントです。
湿度がちょうどいいと、部屋の空気がスッキリ感じられたり、住まいのコンディションを保ちやすくなったりします。
逆に、湿度が高すぎたり低すぎたりすると、さまざまな悩みの原因になることも。
ここでは、快適とされる湿度の目安や、湿度バランスが崩れたときに起きやすいこと、さらに湿度と健康の関係について、信頼できる公的情報をもとにわかりやすく紹介していきます。
快適に感じる湿度の目安
室内の湿度が40~60%の範囲にあると、多くの人が「ちょうどいい」と感じやすいと言われています。
この範囲は、カビやダニが発生しにくく、乾燥による肌や喉の不快感も抑えられるため、住まいの環境としても理想的です。
気象庁や厚生労働省の情報でも、快適な住環境づくりの目安としてこの湿度が推奨されています。
湿度が40%未満になると空気が乾燥しやすくなり、肌がカサついたり喉がイガイガしたりといった不快感が出てくることがあります。
逆に、湿度が60%を超えると、部屋の空気が重たく感じたり、カビの発生リスクが高まったりする可能性も。
エアコンや加湿器、除湿機などを上手に使いながら、毎日こまめに湿度をチェックしておくと安心です。
湿度が高い・低いとどうなる?
湿度が高くなりすぎると、部屋の中がジメジメして快適さが損なわれるだけでなく、カビやダニが発生しやすくなります。
とくに浴室やキッチン、洗濯物を部屋干しするスペースなどは湿気がこもりやすく、注意が必要です。
カビやダニが増えると、壁や家具が傷んだり、生活空間に影響が出たりすることもあります。
一方、湿度が低すぎると空気が乾燥し、肌や喉に違和感を感じやすくなったり、静電気が発生しやすくなったりします。
乾燥した空気はウイルスが空中に長くとどまりやすいとも言われているため、冬場などの乾燥する季節は特に湿度管理が大切です。
季節や天気に合わせて、加湿・除湿のバランスを意識することが、住み心地のよい環境をキープするカギになります。
湿度管理が健康に与える影響
室内の湿度が適切に保たれていると、心地よく過ごせるだけでなく、健康面にも良い影響があります。
湿度が高すぎると、カビやダニが繁殖しやすくなり、それが空気中に広がると、アレルギーの原因になる場合もあります。
逆に、湿度が低すぎると、喉や肌が乾燥しやすくなり、風邪をひきやすくなることも。
また、インフルエンザなどのウイルスが乾燥した空気中で活動しやすくなるとも言われています。
こうした理由から、湿度を40~60%の間に保つことが健康的な暮らしの土台となります。
加湿器や除湿機を活用したり、こまめに換気をしたりすることで、湿度をコントロールしやすくなります。
快適な室内環境づくりのためにも、湿度管理は毎日の習慣として取り入れていきたいですね。
快適な湿度を保つための対策

季節によって湿度が大きく変わる日本では、快適な室内環境をキープするために湿度管理が欠かせません。
夏はジメジメ、冬はカラカラ…そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、湿度を下げたいとき・上げたいときの具体的な対策や、便利な湿気・湿度対策グッズについてご紹介します。
湿度を下げる方法(除湿・換気など)
室内がジメジメして不快に感じるときは、湿度を下げる工夫が必要です。
まず手軽にできるのが「換気」です。
窓を開けて空気を入れ替えるだけでも、こもった湿気を外に逃がすことができます。
特に朝や湿度の低い時間帯を狙って換気すると、より効率的に除湿できますよ。
さらに、換気扇やサーキュレーターを使って空気を循環させるのも効果的です。
空気の流れができることで、湿気が一か所にたまるのを防ぎやすくなります。
加えて、エアコンの除湿機能や除湿機を使えば、気温をあまり変えずに湿度だけを調整できて便利です。
押し入れやクローゼットなど、湿気がこもりがちな場所には市販の除湿剤を置いておくと安心。
こうした湿度対策は、住まいを快適に保つための基本となっています。
湿度を上げる方法(加湿・室内干しなど)
乾燥が気になる冬場や、暖房をよく使う時期には、湿度を上げる工夫が必要です。
まず思い浮かぶのが「加湿器」。
電源を入れるだけで手軽に湿度を調整できるので、特に空気が乾燥しやすい地域では大活躍します。
また、洗濯物を室内に干すのもおすすめ。
乾く過程で水分が空気中に広がるため、自然に加湿ができます。
ほかにも、バケツやコップに水を入れて部屋に置いたり、観葉植物を飾ったり、霧吹きでカーテンや空中に水をまいたりするのも、ちょっとした加湿方法として効果的です。
ただし、加湿のしすぎには注意が必要です。
湿度が高くなりすぎると、カビやダニが発生しやすくなるため、湿度計を使って40〜60%の範囲を目安に調整しましょう。
これらの加湿方法は、住環境の専門家や公的なガイドラインでも紹介されており、安心して取り入れやすい対策です。
おすすめの湿気・湿度対策グッズ
湿度のコントロールには、専用の便利グッズを活用するのが近道です。
まずは、部屋全体の湿度を管理しやすい「除湿機」や「加湿器」。
最近では、自動で湿度を感知して調整してくれるモデルもあり、シーズンを問わず快適な室内環境を保ちやすくなっています。
クローゼットや押し入れには、置き型の除湿剤やシリカゲルタイプの吸湿剤がぴったりです。
スペースが限られていても使いやすく、湿気がこもりがちな場所の湿度対策に役立ちます。
そして何より忘れてはいけないのが「湿度計」。
見た目がおしゃれなインテリア風のものから、温度とセットで表示してくれるタイプまで、さまざまな種類があります。
現在の湿度を「見える化」することで、必要以上の加湿・除湿を防ぐことができ、無駄な電気代の節約にもつながります。
観葉植物も自然な加湿効果が期待できるアイテムです。
緑のある暮らしは気分もリフレッシュできるので、一石二鳥。
これらのグッズは、安心して取り入れられるアイテムばかりです。
エアコンと除湿機能の使い分け

エアコンの冷房と除湿、それぞれの機能を上手に使い分けることで、一年を通して快適な室内環境を保ちやすくなります。
とくに湿度のコントロールは、ムシムシした日も乾燥しがちな日も心地よく過ごすカギになります。
ここでは、冷房と除湿の仕組みの違いや、エアコンを使って効果的に湿度をコントロールする方法、省エネを意識しながら快適さを保つコツをご紹介します。
冷房と除湿の違いと仕組み
冷房と除湿はどちらもエアコンの機能ですが、それぞれの目的が少し違います。
冷房は文字通り「部屋を冷やす」のが目的。
設定した温度まで空気を冷たくして、暑さをやわらげてくれます。
一方で、除湿は「空気中の水分を減らす」ことが主な役割です。
除湿には主に「弱冷房除湿」と「再熱除湿」という2つの方式があります。
弱冷房除湿は、空気を冷やして湿気を取り除いた後、そのまま冷たい空気を室内に戻します。
なので、湿度も下がりますが温度も少し下がってひんやり感じることもあります。
再熱除湿は一度冷やした空気をあたため直してから戻す方式なので、室温をあまり下げずに湿度だけ調整できるのが特徴です。
湿気は気になるけど、肌寒さは避けたいときに役立ちます。
それぞれの特徴を知っておくと、季節や体調に合わせて快適に過ごせるエアコンの使い方が見えてきます。
エアコンで効果的に湿度を調整する方法
湿度を上手にコントロールするには、エアコンの運転モードを状況に応じて切り替えるのがポイントです。
たとえば梅雨時や夏場など、空気がジメジメしている日は「除湿モード」が便利です。
再熱除湿機能がついている機種であれば、気温をあまり下げずに湿度だけ調整できるので、快適に過ごしやすくなります。
また、冷房モードでも設定温度をやや高めにし、湿度を50%前後に保つことで、冷えすぎず快適な空間をキープできます。
湿度が高すぎるとベタつきやカビの原因になりやすく、逆に低すぎると喉や肌の乾燥が気になることもあるため、湿度計を使って今の状態を確認することもおすすめです。
エアコンには「タイマー機能」や「節電モード」なども搭載されている場合が多く、これらを活用すると電気代を抑えつつ効率よく湿度調整が可能です。
エアコンと湿度の関係をしっかり理解すれば、より快適な毎日が過ごせますよ。
省エネ・快適性を両立するポイント
エアコンを使って快適さを保ちつつ、できるだけ電気代も節約したい…というのは多くの方の本音ですよね。
そんなときは、ちょっとした工夫で省エネと快適性を両立することができます。
まず、冷房の設定温度は26〜28℃程度、湿度は50%以下を目安にすると体に負担をかけずに過ごせます。
また、直射日光が室内に入りにくくなるように遮光カーテンを使ったり、窓に断熱フィルムを貼ったりすることで、冷房効率がグッとアップします。
さらに、サーキュレーターや扇風機を併用して空気の流れをつくると、エアコンで冷やした(または除湿した)空気が部屋全体に行き渡りやすくなります。
換気も忘れずに行えば、こもった湿気や熱気を外に出すことができ、より快適な環境に近づきます。
タイマー機能を使って必要なときだけ運転するようにすれば、電気代も抑えられて一石二鳥。
これらのポイントを押さえれば、エアコンを使う夏も冬も快適かつエコな暮らしが叶いやすくなります。
湿気と湿度の違いを理解して快適な暮らしを

「湿気」と「湿度」、どちらも似たような言葉ですが、実は少し意味が違います。
この違いを知っておくことで、毎日の暮らしをもっと快適にする工夫がしやすくなります。
ここでは、湿気と湿度の違いを整理しながら、それぞれの管理のポイントや、季節ごとに気をつけたい対策、さらには健康への影響についてもわかりやすく解説します。
湿気・湿度管理の重要性
湿気と湿度は似た言葉ですが、意味や使われ方には違いがあります。
「湿気」は空気中や物の表面に含まれる水分そのものを指し、カビや結露といった“目に見える形”で感じることが多いです。
一方、「湿度」は空気中にどれだけ水分(=水蒸気)が含まれているかをパーセンテージで表す指標です。
梅雨時や雨の日に「部屋がジメジメする」と感じるのは、湿度が高く空気中の水分が多いためです。
逆に冬場などは湿度が下がり、肌がカサついたり、のどが乾燥したりしやすくなります。
こうした変化を放っておくと、住まいにカビが生えたり、静電気が発生しやすくなったりと、暮らしにさまざまな影響が出ることもあります。
だからこそ、日頃から湿度計を使って空気の状態をチェックし、エアコンの除湿機能や加湿器を上手に取り入れて調整することが大切です。
湿気と湿度の違いを理解して、必要に応じて対策を行うことで、より心地よい住環境を保ちやすくなります。
季節ごとの湿度対策のポイント
湿度の感じ方や影響は季節によって異なります。
梅雨から夏にかけては湿度が上がりやすく、部屋の中がムシムシして不快に感じることが多くなります。
この時期にはエアコンの除湿機能や除湿機、除湿剤などを使って、湿度をコントロールすることが快適さにつながります。
特に押し入れやクローゼットなど、風通しが悪い場所は湿気がこもりがちなので、除湿剤やすのこを活用して通気性を高めましょう。
また、日中はこまめに換気をすることで、湿気の滞留を防ぐことができます。
一方、冬は空気が乾燥しがちで、湿度が30%を下回ることもあります。
そんなときは加湿器を使ったり、洗濯物を部屋干ししたりするのが効果的です。
さらに、観葉植物を置くと自然に湿度が上がるうえに、インテリアとしても楽しめます。
湿度の理想的な範囲はおおむね40~60%といわれており、この範囲を目安に保つことで、1年を通じて過ごしやすい室内環境をキープしやすくなります。
季節ごとの湿度対策を意識することが、快適な暮らしの第一歩です。
湿気と湿度が健康に与える影響
実は、湿気や湿度の状態は私たちの体調にも関係しています。
湿度が高すぎると、カビやダニが発生しやすくなり、それがアレルギーや肌トラブルのきっかけになることもあるといわれています。
特に、湿気がこもりやすい部屋では、目に見えにくいリスクが増えることもあるので注意が必要です。
反対に、冬の乾燥しやすい時期には、湿度が下がりすぎることでのどや肌の乾燥が気になったり、風邪をひきやすくなったりする傾向もあります。
湿度が40%を切るとウイルスが活動しやすくなるともいわれており、適切な湿度を保つことが感染予防の一環としても意識されるようになっています。
このように、湿気や湿度はただの「不快さ」だけでなく、暮らしと健康の両方に関係してくる要素です。
湿度計でこまめにチェックを行いながら、除湿や加湿を状況に応じて取り入れることが、健康的な生活空間づくりにつながります。
日々のちょっとした工夫が、体調管理や快適な住まいの実現につながるのです。
湿気と湿度の違いに関するまとめ
湿気と湿度はよく似た言葉ですが、それぞれ少し意味が違います。
湿度は空気中の水分量をパーセントで表したもので、湿気は水分そのものや、それによって起こるカビや結露などの現象を指します。
この違いを理解することで、室内を快適に保つための対策がとりやすくなります。
湿度が高くなると、部屋がムシムシしたり、カビの原因になったりすることがあります。
逆に湿度が低すぎると、肌や喉が乾燥しやすくなったり、静電気が起きやすくなったりします。
こうしたトラブルを防ぐためにも、湿度は40〜60%の間を目安に保つのが理想とされています。
季節によって湿度の調整方法も変わってきます。
梅雨や夏は除湿と換気、冬は加湿や室内干しなど、時期に合わせた工夫を取り入れることが大切です。
また、湿度のコントロールは暮らしやすさだけでなく、心身のコンディションを整えるうえでも役立つと言われています。
まずは湿度計を使って、今の室内環境をチェックしてみましょう。
ちょっとした意識と工夫で、毎日の暮らしがぐっと心地よくなりますよ。
▼その他の梅雨の湿度対策に関する記事はこちらをチェック▼
梅雨の湿度対策で快適な部屋づくり!部屋干しも安心のカビや臭いを防ぐテクニックまとめ

