
マンションの湿気は階数で違うことをご存じでしょうか?
快適な暮らしを実現するためには、住んでいる階数ごとの湿気の特徴を知り、それに合わせた対策をとることがとても大切です。
なぜなら、湿気のたまりやすさは住まいの階数によって大きく変わるからです。
たとえば1階は地面から近く、外部の湿気の影響を受けやすいため、どうしても室内に湿気がこもりがちです。
一方で3階以上の部屋になると、地面からの湿気は減りますが、方角や間取り、換気の状況次第では結露やカビが発生しやすいこともあります。
たとえば、「1階はカビっぽい気がする」「3階でも窓際に水滴が…」という経験がある方も少なくないのではないでしょうか。
これらの原因は、階数だけでなく部屋の向きや周辺環境、そして家具の配置など、さまざまな要素が絡み合っているのです。
つまり、マンションで湿気を防ぐには「階数」だけに注目するのではなく、「自分の住まいの条件に合った湿気対策」を取り入れることがポイントになります。
この記事では、階数ごとの湿気の傾向や、日常でできる具体的な対策、快適な空間づくりのコツまで、わかりやすくまとめています。
「なんだか最近、部屋がジメジメしてる」「これから引っ越しを考えているけど、湿気が心配…」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
あなたの暮らしがより快適になるヒントが見つかるかもしれません。
▼その他の梅雨の湿度対策に関する記事はこちらをチェック▼
梅雨の湿度対策で快適な部屋づくり!部屋干しも安心のカビや臭いを防ぐテクニックまとめ
マンションの湿気は階数で違う?

「マンションの湿気って、階数によって違うのかな?」と気になったことはありませんか?
実は、住んでいる階によって湿気のたまりやすさやカビが発生しやすい条件が変わってきます。
ここでは、低層階と高層階それぞれの湿気の特徴や、階ごとのカビリスクについて詳しく解説していきます。
部屋選びや住み心地を重視する方は、ぜひ参考にしてください。
低層階(1階・2階)の湿気が多い理由
マンションの1階や2階は、他の階と比べると湿気がこもりやすいと言われています。
その理由のひとつが、地面に近いことで土壌からの湿気が室内に伝わりやすいこと。
特に梅雨の時期や雨が多い季節には、地面の水分が床下や壁を通してじわじわと室内に影響を及ぼします。
また、防犯面やプライバシーの問題から、窓を開けての換気を控える人も多く、空気がこもりがちに。
さらに、1階部分は周囲の建物や木々に囲まれて日当たりや風通しが悪くなることも多く、湿度が高くなりやすい環境が整ってしまいます。
こうした条件が重なることで、結露やカビが発生しやすい状態になってしまうのです。
大手の不動産サイトや住宅関連のメディアでも、低層階では特に湿気対策が重要だと紹介されています。
入居前の内見時には、日当たりや通気性も確認しておくと安心ですね。
高層階と湿気の特徴
高層階は地面から離れているため、地表からの湿気の影響を受けにくいというメリットがあります。
さらに、視界が開けていて風通しや日当たりが良好なことが多く、自然と湿気がこもりにくい環境になりやすいのも特徴です。
とはいえ、高層階だからといって油断は禁物。
現代のマンションは気密性が高く保たれているため、特に冬場は室内と外気の温度差によって窓や壁に結露が発生することがあります。
浴室やキッチンなどの水まわりはどの階でも湿気がこもりやすい場所なので、高層階でも例外ではありません。
また、風通しが良くても換気が十分でないと湿度が高まりやすく、カビの原因になることも。
湿気が気になる季節には、換気扇の使用や除湿機の活用などで、湿度を適切に保つことが大切です。
高層階だからといってノーメンテナンスではなく、しっかり湿度管理を意識しましょう。
階数ごとのカビ発生リスク
マンションの階数によって、カビが発生しやすくなる条件には違いがあります。
1階や2階の低層階は、地面に近いため湿気がたまりやすく、日当たりや換気の面でも不利になることが多いため、カビの発生リスクが高まりがちです。
一方で高層階の場合は、地面からの湿気には強いものの、気密性が高くなることで室内の空気がこもりやすく、結露による湿気がカビの原因となることがあります。
特に浴室、キッチン、収納スペースなどは、どの階でも湿気がたまりやすいので注意が必要です。
また、階数だけでなく、間取りや方角、周辺環境、さらに住む人の生活スタイルによってもカビのリスクは変わってきます。
たとえば、洗濯物の室内干しや長時間の調理なども湿度が上がる原因になります。
どの階に住むにしても、こまめな換気と湿度対策は、快適な暮らしを保つためにとても大切です。
除湿機や換気扇の活用、家具の配置などを工夫しながら、カビの発生を防ぐ環境づくりを心がけましょう。
マンション1階の湿気がひどい理由
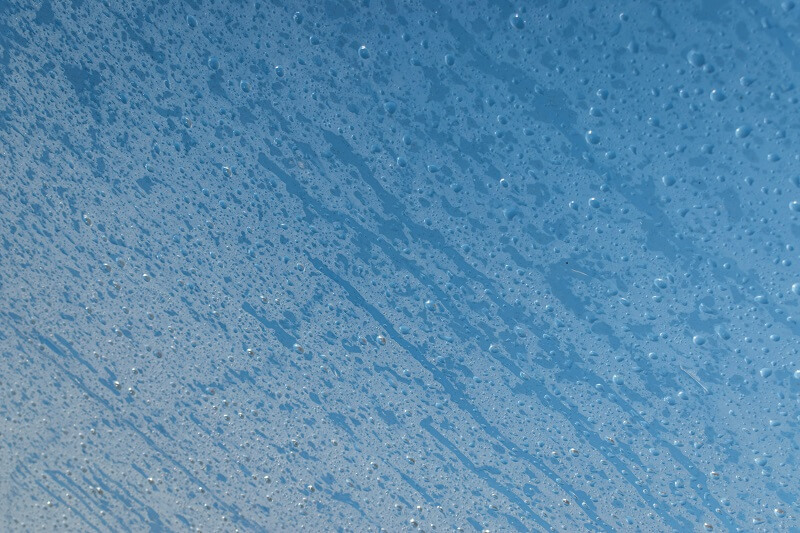
「マンションの1階ってなんだか湿っぽい…」と感じる方は意外と多いです。
実はこれ、建物の構造や地面との距離、周囲の環境など、いくつかの条件が重なって起こる現象なんです。
この記事では、地面からの湿気の影響や、気密性・断熱性との関係、さらには周辺環境が湿気にどう影響するのかを、わかりやすく解説していきます。
地面からの湿気の影響
マンションの1階は、地面に最も近い場所にあるため、どうしても地中や地表から上がってくる湿気の影響を受けやすくなります。
特に梅雨時や雨が続く季節は、地面に含まれる水分が建物の床下を通って室内まで伝わってくることがあります。
床下の通気が十分でないと、湿気がたまりやすく、室内の湿度が上がってしまうのです。
地域の地質や土地の性質によっても湿気の感じ方には差があります。
たとえば、もともと湿地だった場所や水はけの悪い土地では、1階の湿気トラブルが起きやすい傾向があります。
また、床や壁に結露ができやすくなったり、押し入れやクローゼットの中がムシムシするような状態になりやすいのも1階の特徴です。
そんな湿気対策としては、こまめな換気を心がけたり、家具を壁から少し離して配置したりすると効果的ですよ。
気密性・断熱性と湿気の関係
最近のマンションは、断熱性や気密性が高くなっているものが多く、外気の影響を受けにくい構造になっています。
これは冷暖房の効率が良くなるというメリットもありますが、その一方で、湿気がこもりやすくなるというデメリットも。
特に1階は、防犯面や外からの視線が気になって、なかなか窓を開けて換気する機会が少なくなりがちです。
外の空気が入りにくくなることで、室内の空気がよどみ、湿気がたまりやすくなります。
また、室内と外気の温度差が大きいと、窓や壁に結露が起きやすく、それが湿度上昇の原因にもなります。
最近は24時間換気システムを備えた住宅も増えていますが、それでも定期的に窓を開けて空気を入れ替えることが、湿気をため込まないポイントになります。
住まいの専門家たちも、「気密性が高い住宅ほど、意識的な換気が大切」とアドバイスしています。
周辺環境が与える影響
マンション1階の湿気問題は、建物自体の構造だけでなく、周辺環境にも大きく左右されます。
たとえば、近くに川や池といった水辺がある場所では、空気中の湿度が高くなる傾向があります。
また、周囲に背の高い建物や大きな樹木が多いと、日当たりや風通しが悪くなってしまい、湿気が抜けにくい状態が続きやすくなります。
日が当たらない時間が長いと室温が上がりにくくなり、部屋の中の湿気もなかなか乾かないのです。
物件を選ぶときには、部屋の中だけでなく、周囲の環境や建物の配置、風の通り道などもチェックしておくのがおすすめです。
住まいの情報サイトでも、「立地や周辺環境は、快適な住まいを作る大切な要素」と紹介されています。
できるだけ日当たりがよく、風が通りやすい場所を選ぶことで、湿気の悩みを減らしやすくなりますよ。
マンションの湿気が日常生活に与える影響
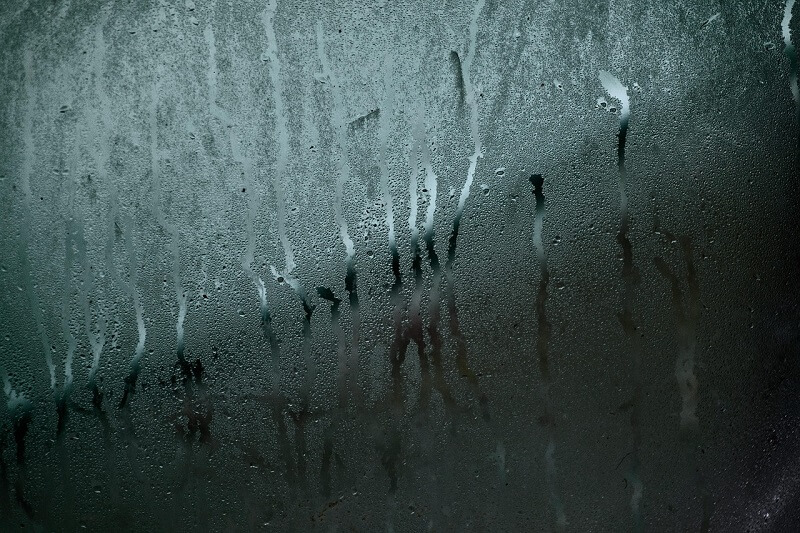
マンションの湿気は、ただ「ジメジメしている」だけでは済まされません。
日々の暮らしの中で、健康や家の設備、家具にまで影響が出ることがあります。
ここでは、具体的にどんな問題が起こりやすいのかを、健康面・住環境・生活の快適さという3つの視点から解説します。
カビ・ダニによる健康への影響
湿気が多いと、カビやダニが発生しやすくなります。
特にマンションの1階など風通しが悪い場所では、空気がよどみやすく、こうした微生物がすみつく環境が整ってしまうのです。
カビやダニが増えると、室内の空気中に小さな粒子が舞い、それを吸い込むことで、鼻がムズムズしたり、咳が出たりすることもあるようです。
敏感な体質の方や小さなお子さん、ご高齢の方にとっては、こうした環境が負担になることもあるため注意が必要です。
さらに、湿度が高い状態が続くと、食品にカビが生えやすくなったり、保存状態が悪化したりすることもあります。
清潔で快適な空間を保つためには、日頃からしっかり換気をすることや、エアコンの除湿機能、サーキュレーターなどを活用して空気の流れを意識するのが効果的です。
結露やニオイのトラブル
室内の湿度が高いと、窓ガラスや壁に水滴がつく「結露」が発生しやすくなります。
特に気温差が大きい冬の朝などは、サッシにびっしりと水滴がついていることも。
放っておくと、そこからカビが生えやすくなるため、日々のちょっとした対策が重要です。
また、湿度が高いと洗濯物が乾きにくくなり、生乾きのニオイが気になることもあります。
とくにクローゼットや押し入れ、靴箱などの空気がこもりがちな場所では、こもったような独特のニオイが出やすくなります。
こうしたニオイは、住んでいる本人は気づきにくく、来客時に気まずい思いをすることも。
ニオイや結露を防ぐためには、定期的な換気と除湿の習慣が大切です。
さらに、家具を壁から少し離して配置するなど、空気の通り道を作るだけでも改善しやすくなります。
家具や建材が受けるダメージ
湿気は、家具や建材にも少しずつ影響を与えていきます。
特に木製の家具やフローリングは湿気を吸いやすく、反ったり、黒ずんだりすることも。
壁紙が浮いてきたり、クロスが剥がれてきたりといった劣化が見られる場合もあります。
また、押し入れやクローゼットにしまってある衣類や寝具にも、カビが発生しやすくなることがあるので油断できません。
こうした湿気によるダメージは、見た目だけでなく、修繕や買い替えなどの手間やコストにもつながってしまいます。
家具を長く使いたい方や、住まいの美観・快適さを保ちたい方にとっては、湿度管理がとても大切なポイントです。
湿気対策としては、除湿機や吸湿シートを活用したり、定期的に収納内をチェックして空気の入れ替えをするなどの小さな工夫が効果的です。
マンションで湿気がたまりやすい場所

マンション暮らしでは、「なんだかジメジメしてるな…」と感じることがあるかもしれません。
実は、湿気がたまりやすい場所にはある程度の共通点があります。
どこに湿気がこもりやすいのかを知っておくと、日々のちょっとした対策にもつながります。
ここでは、特に湿気が気になりやすい「水回り」「窓周辺」「収納スペース」の3か所について、それぞれの注意点や対策のヒントをご紹介します。
水回り(浴室・洗面所・キッチン)
浴室や洗面所、キッチンといった水回りは、毎日の生活の中でも湿気が発生しやすい場所です。
入浴や料理、洗顔など、何かと水を使う場面が多いため、自然と水蒸気がこもりがちになります。
お風呂のあとに浴室内がモワッとするのは、空気中に湿気が溜まっているから。
換気扇を回していても、こまめな拭き取りや窓を開けるといった工夫がないと、湿気が抜けにくいことがあります。
また、洗面所やキッチンでも、濡れたタオルや洗い物の水分が残っていると、ジメジメ感の原因になります。
こうした状態が続くと、カビやぬめりの発生リスクが高まるため、こまめな換気や掃除が欠かせません。
特に、夜間に湿気がこもりやすいので、タイマー機能付きの換気扇を使うのもおすすめです。
住まいに関する専門サイトでも、水回りは湿度管理が大事な場所としてたびたび取り上げられています。
窓周辺・サッシ
窓のまわりやサッシ部分も、湿気が溜まりやすい代表的なポイントです。
特に冬場や梅雨どきなどは、室内と外の温度差が大きくなり、結露が発生しやすくなります。
朝、カーテンを開けたら窓がびっしょり濡れていた…という経験は、多くの方にとっておなじみかもしれませんね。
この結露を放っておくと、水分が溜まって窓枠にカビが発生したり、床材が傷んでしまったりすることがあります。
さらに、北向きの部屋や1階の住戸は特に湿気が抜けにくく、結露が目立ちやすい傾向にあります。
家具を窓際にぴったり置いてしまうと、空気が循環しづらくなり、湿気が逃げ場を失ってしまうことも。
湿度対策としては、こまめに窓を開けて換気することに加え、結露を見つけたらすぐに拭き取る習慣をつけると安心です。
専門家の情報によると、窓まわりの空間を確保して風通しをよくするだけでも、湿気の溜まり方がかなり変わるそうです。
収納・押入れ・クローゼット
押入れやクローゼット、収納棚などの「閉じられた空間」も、実は湿気がたまりやすい要注意エリアです。
これらの場所はふだん扉を閉めていることが多いため、空気の流れが滞りがち。
そのため、湿気がこもってしまうと、衣類や布団、書類などにカビが発生するリスクが高まります。
特に梅雨や冬場は、気温差による結露の影響も受けやすく、湿度管理が一層大切になります。
効果的な対策としては、定期的に扉を開けて空気を入れ替えること、湿気が気になる場合は除湿剤や調湿シートを活用するのも一つの方法です。
また、物を詰め込みすぎないようにすることで、空気の流れが生まれ、湿気がこもりにくくなります。
湿度計を設置して、目に見えない湿気の状態をチェックするのもおすすめです。
整理整頓を意識することで、湿気によるダメージを防ぐだけでなく、収納スペースの使い勝手もぐっと良くなりますよ。
マンションの階数別の湿気対策とカビ予防法

マンションでは、階数や部屋の位置によって湿気のたまり方が少しずつ変わります。
でも、どの階でも共通して言えるのは、毎日のちょっとした工夫で快適な住まいをキープできるということです。
ここでは、湿気対策の基本となる換気や除湿のポイントから、家具の置き方、便利なアイテムの活用法まで、実践しやすい方法をわかりやすくご紹介します。
換気・除湿の基本
湿気対策の基本といえば、やはり「換気」と「除湿」です。
マンションの室内は気密性が高く、空気がこもりやすいため、意識的に風通しを良くすることが大切です。
晴れた日には、できるだけ窓を開けて外の空気を取り込みましょう。
特に湿気がこもりやすい浴室やキッチンでは、調理後や入浴後に換気扇をしばらく回し続けるのが効果的です。
1階や風通しが悪い部屋では、サーキュレーターや扇風機を使って空気を循環させるのもおすすめです。
窓を開けにくい日には、エアコンの除湿機能や除湿機を活用して、室内の湿度を40〜60%に保つのが理想的とされています。
湿度計を設置すれば、湿度の変化にすぐ気づけて対策しやすくなります。
毎日の換気と除湿の積み重ねが、カビのリスクを減らし、心地よい空間づくりにつながります。
家具配置や収納の工夫
家具や収納の配置を少し意識するだけでも、湿気対策になります。
大きな家具を壁にぴったりつけてしまうと、空気の流れが悪くなり、その部分に湿気がたまりやすくなります。
家具と壁の間に5cm以上のすき間をあけることで、空気が通りやすくなり湿気がこもりにくくなります。
また、押入れやクローゼットも詰め込みすぎに注意しましょう。
物がぎゅうぎゅうに入っていると空気が循環せず、湿気がこもる原因に。
適度に空間を空けたり、通気性のいい収納グッズを活用したりすることで、湿気対策につながります。
脚付きの家具やすのこを使うのもおすすめです。
特に梅雨時や冬場は、湿度が上がりやすいので、収納の中もこまめに換気したり、湿度に気をつけながら整理整頓を心がけましょう。
おすすめの湿気対策アイテム
湿気対策には、市販の便利グッズを上手に使うのもポイントです。
除湿機やエアコンの除湿機能は、室内の湿度をコントロールしやすくしてくれるので、特に雨の日や湿気がたまりやすい1階の部屋では頼りになります。
また、サーキュレーターや扇風機を使って空気を循環させることで、湿気が1か所に集中しにくくなります。
クローゼットや押入れ、靴箱などには、使い捨てタイプの除湿剤や湿気取りシートが手軽で便利です。
最近では、おしゃれなデザインや繰り返し使えるタイプも増えているので、用途や好みに合わせて選べます。
また、湿度計をひとつ置いておくと、湿度が高くなっているタイミングがわかり、早めの対策につなげやすくなります。
アイテムを組み合わせて使うことで、自分の住まいに合った湿気対策がしやすくなりますよ。
マンションの物件選びで注意したい湿気リスク

マンションを選ぶときは、立地や間取りだけでなく「湿気がたまりにくいかどうか」もチェックしておきたい大切なポイントです。
湿気対策が不十分だと、住んでから結露やカビに悩まされることも…。
ここでは、内覧時に見るべきチェックポイントや、周辺環境・立地による湿気の影響、建物の管理状態やリフォーム歴について、事前に確認しておきたいポイントをまとめてご紹介します。
内覧時に確認すべきポイント
マンションの内覧では、間取りや設備だけでなく「湿気がこもりやすい構造かどうか」も注目したいところです。
まず確認したいのは、窓の数や配置、風通しの良さです。
角部屋や二面採光の部屋は空気が流れやすいため、湿気がこもりにくい傾向があります。
実際に窓を開けてみて、風が通るかどうかもチェックしておくと安心です。
また、浴室やキッチンなどの水回りに窓や換気扇があるかどうかも大事なチェックポイントです。
換気が不十分な物件は、湿気がたまりやすくなってしまいます。
そして、壁や天井にシミやカビがないか、クローゼットや押し入れの中まで目視で確認するのがおすすめです。
床や天井裏に点検口がある場合は、開けてもらえるか確認してみましょう。
さらに、築年数や断熱性能にも注目しましょう。
断熱性が低いと冬場に結露が発生しやすくなるため、壁の厚みや窓の仕様も見ておくと良い判断材料になります。
内覧時のちょっとしたチェックが、湿気トラブルを避けるための第一歩です。
周辺環境と立地条件の影響
湿気のたまりやすさは、建物の中だけでなく、その周囲の環境や立地条件にも大きく関わっています。
川や池が近くにある物件は空気中の湿度が高くなりやすいですし、緑が多いエリアも同様に湿気がこもりがちになります。
自然が豊かな環境は魅力的ですが、湿気リスクも頭に入れて選ぶと安心です。
また、高い建物に囲まれていたり、近隣の建物との距離が狭かったりする場合は、日当たりや風通しが悪くなることがあります。
太陽の光が入りにくいと、部屋がジメジメしやすく、カビの原因になることも。
南向きの物件でも、前に高層ビルがあると実際にはあまり日が入らないこともあるので、必ず現地で確認しましょう。
現地を訪れる際は、午前中と午後の両方の時間帯で日当たりや風の通り方を比べてみるのがおすすめです。
実際にその場所の空気感や湿度を体感することで、物件選びの判断がしやすくなります。
周辺環境までしっかり見ておくことが、快適なマンションライフにつながります。
管理状態やリフォーム履歴の確認
物件そのものの状態だけでなく、マンション全体の管理体制がしっかりしているかどうかも、湿気リスクを見極めるうえで大切なポイントです。
共用部分が清潔に保たれているか、水回り設備に不具合がないかなどをチェックしましょう。
エントランスや廊下、ゴミ置き場なども、管理の質がわかる手がかりになります。
築年数が経っているマンションの場合、断熱材や換気設備が古くなっていることも。
過去に大規模修繕工事が行われているか、排水設備の更新がされているかなども確認しておくと安心です。
もし可能であれば、管理人さんや管理組合に質問してみるのも良い方法です。
売主や不動産会社から「修繕履歴」や「長期修繕計画書」を取り寄せて、過去の対応状況を把握しておくこともおすすめです。
過去に水漏れや雨漏りなどのトラブルがあった場合、その影響が残っている可能性もあるため、履歴を見て慎重に判断しましょう。
マンションは長く住む場所だからこそ、見た目だけでなく見えない部分のチェックがとても大切です。
しっかり確認しておくことで、湿気に悩まされない快適な暮らしを手に入れることができます。
マンションの湿気対策で快適な生活を実現するために

マンションで気持ちよく暮らすには、「湿気」とうまく付き合うことが大切です。
階数や間取りによって湿気のたまりやすさには違いがあるので、自分の住まいに合った対策をしていくことがポイントです。
ここでは、住んでいる階数による湿気の傾向、日常的にできる湿気対策、そして快適な空間を保つためのコツをわかりやすくご紹介します。
階数ごとの特徴を理解する
マンションでは住む階数によって、湿気のたまりやすさに違いがあります。
1階は地面に近いため、地中の水分や外気の湿気の影響を受けやすく、どうしても湿気がこもりやすくなりがちです。
換気もしづらいことが多く、気づかないうちにカビが生えやすい環境になることもあります。
2階は1階ほどではないにしても、角部屋でなければ風通しや日当たりがやや弱くなることがあり、油断すると湿気がたまりやすいケースも。
3階以上になると、地面からの湿気の影響は少なくなりますが、今度は部屋の向きや窓の配置によっては結露が出やすくなることがあります。
特に北向きの部屋や、換気が十分にできない間取りの場合、湿気対策が必要になることも。
住まいを選ぶときは、階数だけでなく「どの方角にあるのか」「窓がどれだけ開けられるのか」といった点も合わせてチェックして、自分の生活スタイルに合った湿気対策をしていきましょう。
日常的な湿気対策の徹底
マンションで湿気をためないコツは、毎日のちょっとした習慣にあります。
基本は「こまめな換気」と「空気の循環」です。
晴れた日には窓を開けて空気を入れ替えるだけでも、湿気はかなり軽減されます。
また、浴室やキッチンなどの水回りは湿気がたまりやすい場所なので、使用後は換気扇をしっかり回すことが大切です。
24時間換気システムがある場合は、それを活用するのもおすすめです。
家具の配置も見落としがちですが、壁にぴったりくっつけずに少しすき間をあけて空気が流れるようにすると、カビ予防にもつながります。
押し入れやクローゼットも、物を詰め込みすぎず空間を作ることで湿気がこもりにくくなりますよ。
さらに、湿度計を使って室内の湿度をチェックするのもひとつの方法です。
目安としては40〜60%を保つと快適とされています。
住宅に関する公的サイトでも紹介されているこれらの方法は、毎日の暮らしに取り入れやすく、無理なく続けられる湿気対策です。
健康的な住環境を維持するポイント
快適なマンション生活を続けるためには、湿気対策に加えて、室温や空気の清潔さをバランスよく保つことが大切です。
断熱性の高い建材を使った部屋は、冷暖房効率もよく、結露の発生を抑えやすくなります。
遮熱カーテンや断熱性のある窓フィルムなどを取り入れるのもおすすめです。
また、加湿器や除湿機などの家電を使うときは、定期的な掃除とメンテナンスを忘れずに。
きれいな状態を保つことで、より安心して使い続けることができます。
さらに、空気清浄機や24時間換気機能を活用することで、室内の空気の入れ替えがしやすくなり、湿気だけでなく空気のよどみも防げます。
小さな工夫の積み重ねが、快適で健康的な住まいにつながります。
自分のライフスタイルに合った方法を選び、無理なく続けていくことが、長く心地よく暮らす秘訣です。
マンションの湿気は階数で違うのかに関するまとめ
マンションの湿気対策は、実は住んでいる階数によってポイントが変わってきます。
1階は地面に近いため、外からの湿気の影響を受けやすく、特に雨の日などは室内の湿度が上がりやすくなります。
防犯やプライバシーの関係で窓を開けにくいという事情もあり、湿気がこもりやすい傾向があります。
2階になると湿気の影響は少し軽くなりますが、日当たりや風通しの条件によっては、カビが出やすくなることも。
3階以上は地面からの湿気が届きにくくなるものの、部屋の向きや窓の位置、間取りによっては結露などが起こりやすくなるケースもあります。
ただし、湿気の影響は階数だけでは語れません。
北向きの部屋や日差しが入りにくい部屋、周囲に木々や水辺がある場所では、どの階でも湿気がたまりやすくなります。
また、建物の構造や築年数、換気設備の有無なども大きく関わってきます。
快適に過ごすためには、自分の部屋の特徴をきちんと理解して、こまめな換気や除湿、家具の配置の工夫、湿度計を使った管理など、日常の中でできる湿気対策を積み重ねることが大切です。
これから新しく住まいを探す方は、内覧のときに風通しや湿気の状態、建物の管理状況などもしっかりチェックしておくと安心です。
まずは今のお部屋を見直して、できることから湿気対策を始めてみましょう。
ちょっとした工夫の積み重ねが、快適な暮らしへの第一歩になりますよ。
▼その他の梅雨の湿度対策に関する記事はこちらをチェック▼
梅雨の湿度対策で快適な部屋づくり!部屋干しも安心のカビや臭いを防ぐテクニックまとめ

