
「除湿機の音がうるさい…」そんな風に感じていませんか?
実はこれ、多くの方が一度は悩む問題なんです。
静かな夜や集合住宅、アパートでの使用時に、ゴォーッという低い音や細かい振動が気になって眠れなかった経験、あるのではないでしょうか。
結論から言うと、「除湿機の音がうるさくなった」と感じたときは、設置場所やメンテナンスを見直すことで改善できる可能性が高いです。
その理由は、音の原因が本体の構造だけでなく、ファンやモーターの振動、床や壁の共鳴、さらにはフィルターの汚れなど、複数の要素から成り立っているからです。
例えば、除湿機の下に防振マットを敷くだけで、床に伝わる音や振動がかなりやわらぎます。
最近では100均でも防振グッズが手に入るため、コスパよく音対策できるのも嬉しいポイント。
また、「この音ってどのくらいのレベルなんだろう?」と気になる場合は、一般的な除湿機の運転音は40〜50dB程度とされていますが、静かな部屋ではこの音も意外と気になるもの。
そんなときは静音モードやタイマー機能を使うことで、生活のリズムに合った使い方ができます。
つまり、「うるさいのが当たり前」とあきらめずに、ちょっとした工夫で快適に使えるようになるんです。
この記事では、除湿機の音がうるさい原因とその対策を、わかりやすく紹介していきます。
「最近、音が前より気になるかも?」と思った方は、ぜひ読み進めてみてください。
今すぐ始められる静音対策のヒントがきっと見つかりますよ。
▼その他の梅雨の湿度対策に関する記事はこちらをチェック▼
梅雨の湿度対策で快適な部屋づくり!部屋干しも安心のカビや臭いを防ぐテクニックまとめ
除湿機の音がうるさい

除湿機を使っていて、「思っていたより音が気になる」と感じたことはありませんか?
特に夜や静かな部屋で使うと、動作音が思いのほか響くことも。
ここでは、除湿機の音が大きく感じられる理由や、使い方によって変わる騒音レベル、実際にユーザーが感じている「うるさい」とはどの程度なのかをわかりやすく解説します。
なぜ除湿機は音が大きくなるのか
除湿機の音が気になる主な原因は、本体内部で動いているファンとコンプレッサーによるものです。
ファンは湿気を取り除くために空気を循環させますが、その際に「ゴーッ」という風の音や、わずかな振動音が発生します。
特にコンプレッサー式の除湿機は、冷媒を圧縮する際の作動音が加わるため、音が大きく感じられやすくなります。
また、除湿機を硬い床や壁の近くに置いていると、音が反響してさらに響くことがあります。
木製の家具のそばなども要注意です。
さらに、使い続けるうちにファンにホコリが溜まったり、パーツが摩耗したりすると、運転音が以前より大きくなることも。
こうした現象はどの家庭でも起こり得るため、使用環境やお手入れの頻度が静音性に影響すると言えます。
メーカーの公式サイトや家電専門メディアでも、音の原因としてこうした要素が挙げられています。
運転モード別の騒音レベルの違い
除湿機は、選ぶ運転モードによって音の大きさが大きく変わるのが特徴です。
湿気が多い梅雨時期に活躍する「強運転モード」や、洗濯物を乾かす「衣類乾燥モード」を使うと、ファンとコンプレッサーがフルパワーで動くため、騒音レベルが50dB前後になることが一般的です。
このくらいの音は、冷蔵庫の動作音や普通の会話の音量に近く、日中であれば気にならないという方も多いです。
一方、「弱運転モード」や「静音モード」に切り替えると、ファンの回転数やコンプレッサーの動作が抑えられ、騒音レベルは35〜40dBほどまで下がることがあります。
これは図書館の中や、夜の静かな住宅街と同じくらいの静けさとされており、就寝時にも使いやすいモードです。
商品によってはスペック表にモードごとの騒音値が明記されていることがあるので、購入前にチェックしておくのがおすすめです。
比較サイトなどでも、騒音レベルを基準に評価されている機種もあるので参考にしてみましょう。
ユーザーが感じる「うるさい」とはどの程度か
除湿機の音に対する感じ方は人それぞれですが、一般的には40dBを超えると「少しうるさいかも」と感じる人が増えてくる傾向があります。
特に夜の静かな時間帯や、寝室・書斎など音が響きやすい環境では、わずかな運転音でも敏感に感じてしまうことがあります。
実際に家電レビューやユーザーの声を見てみると、「寝るときに音が気になって除湿機を止めた」「低く響く音が心地よくない」といった意見が多数見られます。
木造住宅やマンションなどでは、建物の構造によって音が響きやすく、同じ機種でも環境次第で騒音の感じ方が変わることもあります。
さらに、「ブーン」という低音や振動音は、意識すると気になってしまうという声も多く見られます。
これは音の種類によって不快に感じる度合いが変わるためで、一定のリズムや高周波よりも、低く響く持続音のほうがストレスに感じやすいようです。
除湿機を選ぶときは、騒音値だけでなく、実際の音の種類や使用環境も考慮して選ぶことがポイントになります。
除湿機の音はどのくらい?
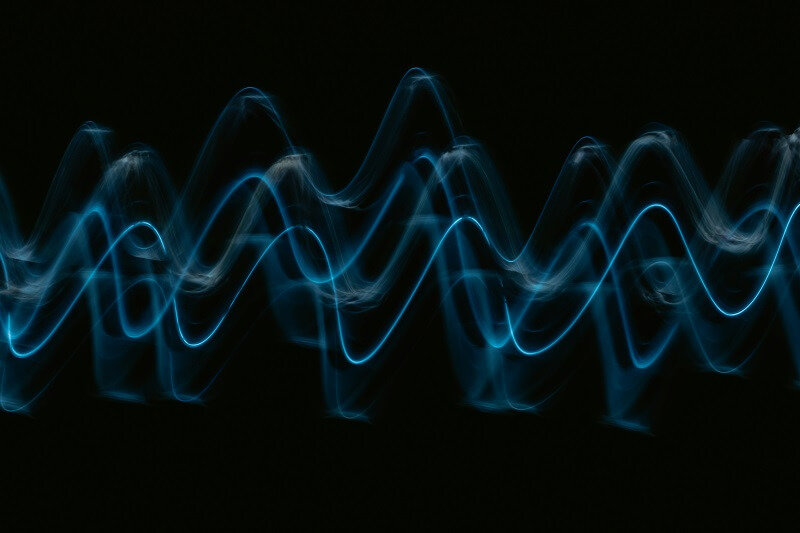
除湿機を使い始めると、「意外と音が大きい」「寝室で使うにはうるさくないかな?」といった疑問が出てくることがあります。
実際にどのくらいの音がするのか、他の家電との比較や静音タイプの選び方を知っておくと、自分に合った機種を選びやすくなります。
ここでは、除湿機の騒音レベルをわかりやすく解説していきます。
除湿機の平均的な騒音レベル(dB)
家庭用の除湿機が出す音の大きさは、一般的に40~50dB(デシベル)くらいとされています。
これは、静かなオフィスや図書館の中と同じくらいの静けさから、普通の会話と同程度の音量まで幅があるということです。
除湿の仕組みによっても音の感じ方は変わります。
コンプレッサー式の除湿機は除湿能力が高い反面、強モードで運転すると50dBを超えることがあります。
一方、静音モードを使えば40dB前後になるモデルも多く、夜間でも気になりにくいレベルです。
さらに、デシカント式やペルチェ式といったタイプは、構造上コンプレッサーがないため、比較的静かに動くものが多いです。
中には30dB台という静けさのモデルもあり、寝室や子ども部屋などにも向いています。
こうした情報は、メーカーの製品情報ページや家電比較サイトに掲載されているので、購入前に確認しておくと安心です。
音の感じ方は人それぞれですが、数字を基準にすることで選びやすくなります。
他の家電製品との音の比較
除湿機の音がどれくらいかイメージしにくいときは、普段使っている家電製品と比べてみるのが一番です。
冷蔵庫の運転音は約40dB、エアコンの室外機は50dB程度、洗濯機になると60dB前後の音がします。
除湿機はだいたい冷蔵庫とエアコンの中間くらいの音を出していると考えるとわかりやすいでしょう。
通常の除湿モードであれば、日常生活の中であまり気にならないレベルですが、衣類乾燥モードや強モードに切り替えると音も大きくなり、洗濯機に近いような音量に感じることもあります。
そのため、「夜は静かに使いたい」「作業や勉強の邪魔をしたくない」と思っている方は、静音モードがある機種や音が小さいタイプを選ぶのがおすすめです。
特に静音重視の方には、ペルチェ式の除湿機が向いています。
これは冷却装置の仕組みがシンプルなため、動作音がとても静かです。
中にはパソコンのファン程度(約30dB)の音しか出さないモデルもあり、在宅ワーク中や夜間の使用にぴったりです。
静音性に優れたおすすめ除湿機
除湿機の音が気になる方にとって、「どれだけ静かに使えるか」はとても重要なポイントです。
静音性を重視して選ぶなら、まずは製品のスペック表にある騒音レベルの数値をチェックしましょう。
一般的に40dB以下であれば、静音性が高いと言われています。
最近では、コンプレッサー式でも運転モードによって音が抑えられる製品が増えてきました。
「弱運転」や「おやすみモード」といった名前で静音モードが用意されている機種も多く、就寝時や集中したいときにも安心して使えます。
また、もともと構造が静かなデシカント式やペルチェ式も選択肢に入れてみましょう。
選ぶ際には、家電比較サイトや通販サイトのレビューも参考になります。
「音が気にならなかった」「寝室で使っても快適」といったリアルな声は、とても参考になります。
特に、「寝室用」や「子ども部屋用」として紹介されているモデルは、静音性が高い傾向にあります。
設置する場所や使う時間帯、使用目的に合わせて静音性と除湿力のバランスを考えることで、より満足のいく1台を見つけることができるはずです。
除湿機がうるさいときの対策

除湿機の音が思ったより大きくて気になる…そんなときは、ちょっとした工夫で快適に使えるようになるかもしれません。
ここでは、家庭でできる静音対策をわかりやすくご紹介します。
設置場所を見直すポイント
除湿機の音が気になるとき、まず見直してほしいのが設置場所です。
壁や家具の近くに置いていると、音が反射して意外と響いてしまうことがあります。
可能であれば、部屋の中央付近や周囲に物が少ないスペースに置くことで、音が拡散されて気になりにくくなる傾向があります。
また、床がフローリングやタイルなど硬い素材だと、振動がダイレクトに響くことも。
そんなときはカーペットや防振マットを下に敷くだけでも、グンと静かに感じられることがあります。
とくに深夜の使用時など、周囲が静かな環境では音が目立ちやすいので、設置場所の見直しはとても大切です。
実際に家電レビューサイトでも「設置場所を変えたら気にならなくなった」という声が多く見られます。
快適に使うためにも、まずは設置場所のチェックから始めてみてください。
静音運転モードの活用方法
最近の除湿機には、静音モードや弱運転モードなど、音を抑えた使い方ができる機種が増えてきています。
特に夜間や寝室での使用には、この静音モードが役立ちます。
通常運転ではファンやコンプレッサーがしっかり動くため音も大きめですが、静音モードなら出力を抑えながら運転してくれるので、就寝中でも安心して使えるのが魅力です。
衣類乾燥モードや強運転モードは、除湿力は高いものの、そのぶん音も大きくなる傾向があります。
そのため、これらのモードは日中や家事中など、多少の音が気にならない時間帯に使うのがおすすめです。
購入を検討している方は、メーカー公式サイトや家電比較サイトで「静音モードあり」「運転音◯dB」などのスペックを確認してみてください。
レビューでも「夜でも気にならない」「静音設計がうれしい」といったコメントが多く、静音性は選ぶうえで重要なポイントとなっています。
目的に応じて運転モードを切り替えることで、騒音をぐっと減らすことができますよ。
簡単にできる防音・防振対策
除湿機の音対策としてすぐに取り入れやすいのが、防音・防振グッズの活用です。
防振マットや厚手のカーペットを除湿機の下に敷くだけで、振動が床に伝わるのをやわらげ、ゴーッという低い音が軽減されることがあります。
ジェルタイプのパッドやゴム素材のマットなど、ホームセンターやネットショップ、100円ショップでも気軽に手に入るのでコスパも抜群です。
設置もとても簡単なので、騒音が気になるときにすぐ試せるのも大きなメリットです。
実際に使った方のレビューを見てみると、「振動音がしなくなった」「床への響きが減った」という声が多く、防音対策として一定の効果を感じている人が多いようです。
特にフローリングの部屋では違いを実感しやすいでしょう。
除湿機の音がストレスになってしまう前に、こうしたアイテムを使って快適に過ごせる環境を整えてみてください。
ちょっとした工夫が、毎日の快適さに大きな差を生んでくれます。
除湿機がうるさくなったのは故障?

「なんだか最近、除湿機の音が気になる…」そんなふうに感じたら、もしかすると何かしらのトラブルが起きているサインかもしれません。
今回は、気になる異音の種類や自分でできる確認方法、修理や買い替えを検討するタイミングについて、わかりやすくご紹介します。
故障のサインとなる異音の種類
普段は静かに動いていた除湿機から、「ジジジ」「ガタガタ」「ブーン」といったいつもと違う音が聞こえるようになったら注意が必要です。
こういった異音は、ファンやモーターの劣化、内部に何か異物が入り込んだこと、あるいは部品がゆるんでいることなどが原因として考えられます。
また、「擦れるような音」「振動が大きい」といった症状も見逃せません。
中には湿度センサーや温度センサーの不具合が音に表れるケースもあり、異音とあわせてエラーランプが点滅したり、液晶にエラーコードが出たりすることもあります。
こうした場合は無理に使い続けず、まずは取扱説明書を確認して、メーカーのサポートページや問い合わせ窓口に相談するのが安心です。
異音が出ている=必ずしも故障とは限りませんが、長く安心して使うためにも、違和感を覚えたら早めに対処することが大切です。
セルフチェックできる原因と対処法
除湿機の音がいつもより大きく感じられたときは、まず自分で確認できるポイントをチェックしてみましょう。
特に次の3つは簡単にできて、効果的な確認ポイントです。
1つ目は、水タンクがきちんとセットされているかどうか。
ズレていると振動やカタカタ音の原因になることがあります。
2つ目は、フィルターにホコリがたまっていないか。
フィルターの目詰まりは風の流れを妨げ、結果的にモーターに負担がかかって音が大きくなることがあります。
そして3つ目は、除湿機の置き場所です。
不安定な場所や傾いた床に置くと、振動音が増すことがあります。
また、しばらく使っていなかった除湿機や、引っ越しなどで移動させたあとは、内部の部品が一時的にうまく動いていない可能性もあります。
一度電源を切って、水平な場所に置き直してから再起動するだけでも改善することがあります。
これらのセルフチェックを行っても異音やエラーが続く場合は、自己判断で分解したりせず、メーカーのサポートへ相談しましょう。
日頃からフィルターやタンクの掃除をしておくことも、異常を防ぐポイントです。
修理・買い替えの判断基準
チェックしても音が直らなかったり、エラー表示が消えない場合は、修理か買い替えを考えるタイミングです。
購入から1年以内であれば、保証期間内で修理費用が無料になることもあるので、まずは購入時の保証内容を確認してみましょう。
一方で、すでに数年以上使っている除湿機の場合、修理に出しても費用が高くついてしまうこともあります。
そのようなときは、新しいモデルへの買い替えも視野に入れてみてください。
最近の除湿機は、静音性や省エネ性が向上しており、使い勝手もアップしています。
「使えるから」と無理にそのまま使い続けると、さらに不具合が大きくなってしまう可能性もあるため、判断に迷ったら専門の業者やメーカーに相談するのが安心です。
除湿機は日々の快適さに直結する家電なので、不調を感じたら早めに対応しておくことが大切です。
除湿機の防振マットは100均である?

除湿機の音や振動が気になったとき、床との間に防振マットを敷くだけで、だいぶ印象が変わることがあります。
最近では、100円ショップでも手軽に使える防振グッズが豊富にそろっているため、コストをかけずに振動や騒音対策ができると人気です。
ここでは、100均で手に入るアイテムの種類や選び方、節約しながら快適に過ごすための防振・防音対策の工夫をご紹介します。
100均で手に入る防振グッズの種類
100円ショップには、除湿機の振動や騒音をやわらげるグッズがいろいろと揃っています。
ゴム製の防振パッドやスポンジ素材のクッションシート、ジェルタイプの滑り止めなどがあります。
これらはもともと洗濯機や冷蔵庫用として売られていることが多いですが、除湿機にも問題なく使えます。
形状も四角形や円形などバリエーションが豊富で、用途に合わせて選びやすいのも魅力です。
売り場は「洗濯用品」「キッチン用品」「DIYグッズ」コーナーなどにあることが多く、店員さんに聞いてみるとスムーズに見つかります。
価格が手頃なので、初めて防振対策を試す方にもぴったりです。
防振マットの効果と選び方
防振マットを使うと、除湿機の振動や運転音が床に響くのを軽減できることがあります。
特にフローリングや畳の上では、直接置くよりもマットを挟むことで音の伝わり方が変わり、静かに感じられることが多いです。
選ぶときは、マットの素材や厚みに注目しましょう。
ゴム製やジェル素材のものはクッション性があり、除湿機の重みをしっかり受け止めてくれるのでおすすめです。
厚さは5〜10mm程度あると、防振効果を実感しやすい傾向にあります。
除湿機の大きさや置き場所に合わせて、マットのサイズや形もチェックしておくと安心です。
置くだけで手軽に使えるため、静音対策のひとつとして取り入れてみるとよいでしょう。
コスパ重視の防音・防振対策アイデア
「なるべくお金をかけずに騒音対策したい!」という方には、100均グッズを使った工夫がおすすめです。
防振マットのほかにも、ジョイントマットやラグ、厚手のカーペットなどを敷くことで振動を吸収しやすくなります。
さらに、家具用のクッションパッドや滑り止めシートも、除湿機の足元に設置することで効果を感じやすくなることがあります。
これらのグッズは工具不要で使えるものばかりなので、設置や移動もラクラクです。
ネットやSNSでは「100均グッズを使って除湿機の音が気にならなくなった」という声も多く見られます。
毎日使う除湿機だからこそ、ちょっとした工夫で快適さがアップしますよ。
費用を抑えつつ静かに使いたい方は、ぜひ100均アイテムを取り入れてみてください。
除湿機の音を抑えるための最新技術と製品トレンド

除湿機の音が気になって眠れない…なんて経験はありませんか?
最近は、静音性に力を入れた除湿機が増えていて、音のストレスを軽減できるモデルも登場しています。
ここでは、最新の静音技術やおすすめの機種、そして今後注目の製品トレンドまで、静かな除湿機を選ぶためのヒントをまとめてご紹介します。
静音化技術の進化と特徴
ここ数年で、除湿機の静音性能は大きく進化しています。
これまで「音がうるさい」と敬遠されがちだったコンプレッサー式の除湿機でも、運転音を抑えるための工夫が多数取り入れられるようになりました。
ファンやモーターの構造を見直し、振動が発生しにくい設計になっていたり、本体内部に防音素材を使うことで、運転音を吸収・拡散するようになってきています。
また、風の流れを整える「風路設計」が工夫されることで、空気がスムーズに流れ、耳障りな音が発生しにくくなっています。
こうした技術はメーカーの公式情報にも掲載されており、製品のレビューでも「以前より静かになった」と感じるユーザーの声が多く見られます。
寝室や書斎など、静かな環境で使いたい方にとっては、こうした静音技術の進化は大きなメリット。
除湿能力だけでなく、音への配慮も選ぶポイントとして意識してみると、より快適な使い心地が得られます。
最新モデルの静音性能比較
静音性を重視した最新の除湿機モデルでは、「静音モード」や「ナイトモード」が搭載されているものが多く登場しています。
これらのモードでは、運転音が約30〜45dB程度に抑えられており、図書館やささやき声と同じくらいの静かさとされています。
コンプレッサー式のモデルはパワフルですが、一般的に音がやや大きめ。
ただし、最近のモデルでは静音モードで40dB前後まで音が抑えられており、夜間の使用にも適しています。
さらに、デシカント式やペルチェ式といった方式の除湿機は構造上音が静かで、35dB程度の製品もあります。
静かな環境で過ごしたい方にはこちらの方式もおすすめです。
また、衣類乾燥モードなどパワーを必要とするモードではやや音が大きくなる傾向がありますが、使い分けることで快適に使用できます。
購入時には、製品スペックの騒音値(dB表記)を確認し、ユーザーレビューや比較サイトで実際の使用感をチェックするのがポイントです。
今後の製品トレンドと注目ポイント
除湿機市場では、これからも「より静かに、より使いやすく」という流れが続いていくと予想されています。
静音性を保ちつつ除湿力もアップしたモデルや、タンク容量が大きくなって給水の手間が減るモデル、連続排水に対応した便利な機種など、さまざまな進化が見られます。
また、省エネ運転ができる自動制御センサーや、就寝中でも安心して使えるタイマー機能が標準装備される製品も増えています。
こうした機能は日常の中での使い勝手に直結するため、選ぶ際の大きなポイントになるでしょう。
特に今後注目なのが、「40dB以下で動作する静音設計モデル」。
寝室や在宅ワーク中の部屋でも気にならない静かさが評価されており、需要が高まっています。
購入時には、設置場所や使用目的を明確にし、自分のライフスタイルに合った静音機能や便利機能を比較して選ぶと、満足度の高いお買い物ができるはずです。
アパートで除湿機がうるさいけどクレームとかこない?

除湿機は湿気対策に便利なアイテムですが、アパートなどの集合住宅では「音が気になる…」「近所迷惑にならないかな?」と不安に思う方もいるのではないでしょうか。
ここでは、実際にあった音に関するトラブルの事例や、トラブルを避けるための配慮ポイント、クレームを防ぐための対策について、わかりやすく解説します。
集合住宅での騒音トラブル事例
アパートやマンションのような集合住宅では、ちょっとした生活音でも気になることがあります。
除湿機も例外ではなく、「ブーン」という低めの運転音や本体の振動が原因で、下の階や隣室に響いてしまうケースがあるようです。
特にコンプレッサー式の除湿機は、構造上どうしても一定の音や振動が発生しやすい傾向があります。
ネット上の掲示板や生活相談窓口では、「夜中に除湿機の音が気になって眠れない」「壁越しに重低音が響く」といった声が見られます。
木造の建物や築年数の古いアパートでは、音が伝わりやすくなる傾向があるため注意が必要です。
また、鉄筋コンクリート造でも油断は禁物。
静かな夜間や早朝などは、普段以上に音が目立ちやすくなります。
音に対する感じ方には個人差があるので、「自分は気にならないから大丈夫」と思っていても、隣人にとってはストレスになっていることも。
音の問題は、思わぬご近所トラブルにつながることがあるので、事前に対策を考えておくことが大切です。
隣人や管理会社への配慮ポイント
トラブルを防ぐには、周囲へのちょっとした気配りが大事です。
除湿機を壁や床から少し離して設置するだけでも、音の伝わり方がかなり変わります。
防振マットを敷いたり、厚手のラグを活用したりすると、床への振動も抑えやすくなります。
さらに、除湿機を使う時間帯にも注意が必要です。
夜中や早朝など、まわりが静かな時間は、音が響きやすいタイミングです。
なるべく日中に運転するようにしたり、静音モードやタイマー機能を活用して短時間だけ使ったりする工夫が安心です。
もしも音に関する指摘があった場合は、素早く対応するのがポイント。
設置場所を見直したり、運転時間を変えたりと柔軟に対応する姿勢が、ご近所との良好な関係を保つ鍵になります。
また、管理会社から連絡があった場合も、丁寧なやり取りを心がけましょう。
ちょっとした配慮の積み重ねで、快適な暮らしが守られます。
クレームを防ぐための工夫
除湿機の音でトラブルにならないようにするには、日ごろの対策がとても重要です。
まずは、設置場所に防音・防振アイテムを取り入れることが効果的です。
市販の防振マットや厚手のカーペットを敷くことで、床への振動や音の響きを軽減しやすくなります。
また、定期的にフィルターや吸気口のお手入れをすることも大切です。
ホコリがたまると運転効率が落ちて、余計な音が出る原因になることもあります。
メンテナンスをこまめに行うことで、快適な運転をキープできます。
静音設計の除湿機を選ぶのもひとつの手です。
最近は静音性を重視したモデルが多く、口コミサイトでも「音が静かで安心して使える」といった感想が多く見られます。
製品選びの際は、スペック表の騒音レベル(dB表記)やレビューをチェックして、自分の生活スタイルに合ったものを探してみましょう。
万が一、クレームが入ってしまった場合は、感情的にならずに丁寧に対応し、原因を確認して対策をとることが大切です。
こうした配慮を心がけることで、アパートでも安心して除湿機を使うことができますよ。
除湿機の音がうるさいに関するまとめ
除湿機の音が気になるとき、その原因はファンやモーターの振動、設置場所、そして経年劣化やフィルターの汚れなど、意外と身近なところにあることが多いです。
一般的な除湿機の運転音は40〜50dBくらいですが、夜の静かな時間や集合住宅だと「うるさい」と感じる方も少なくありません。
特にコンプレッサー式の除湿機は、低音の響きや本体の振動が強く、木造や古い建物では音が伝わりやすくなる傾向があります。
音の悩みをやわらげるためには、除湿機を壁や床から少し離して設置したり、防音・防振マットを敷くなどの工夫が効果的です。
また、静音モードやタイマー機能をうまく活用すれば、夜間の運転音が気になるシーンでも安心して使いやすくなります。
フィルターの掃除や定期的なメンテナンスを続けることで、余計な振動や異音の予防にもつながります。
集合住宅にお住まいの場合は、ご近所さんへの配慮も忘れずに。
万が一、音に関する指摘があったときは、すぐに対応する姿勢を見せることで、トラブルの回避にもつながります。
最近では、静音性を意識したモデルや、お手頃価格の防音グッズも増えてきました。
住んでいる環境や生活スタイルに合わせて、少しの工夫をするだけで除湿機の使い心地がグンと良くなります。
まずは、設置場所の見直しやメンテナンスから始めてみてはいかがでしょうか?
毎日を快適に過ごすための第一歩として、今日からできる対策をぜひ取り入れてみてください。
▼その他の梅雨の湿度対策に関する記事はこちらをチェック▼
梅雨の湿度対策で快適な部屋づくり!部屋干しも安心のカビや臭いを防ぐテクニックまとめ

