
「ハーブの虫除けは効果ないのでは?」と気になって検索している方は多いのではないでしょうか。
ナチュラルで安心な虫対策を試してみたいけれど、本当に意味があるのか疑問に思っている方もいるかもしれません。
結論から言うと、ハーブには虫が苦手とされる香り成分が含まれており、適切に使えば虫が寄りにくい環境をつくるサポートが期待できます。
そう言える理由は、ミントやレモングラス、蚊連草(かれんそう)などのハーブが放つ香りに、虫が反応しにくくなる傾向があるためです。
実際に、玄関先やベランダ、室内などでハーブを上手に取り入れている方からは、「なんとなく虫が減った気がする」といった声もよく聞かれます。
鉢植えで育てるだけでなく、葉を軽く揉んで香りを広げたり、精油やサシェにして使うことで、香りの拡散力や持続性が高まりやすくなります。
ただし、市販の虫除け剤のように即効性や強い持続力を求めるのは難しいため、あくまで「虫を寄せにくくする補助アイテム」として使うのが現実的です。
つまり「ハーブの虫除けは効果ない」と感じるのは、使い方や期待値によるところも大きいのです。
香りを楽しみながら自然な方法で虫を遠ざけたい方には、ハーブは無理なく続けやすい選択肢です。
まずは自分の生活スタイルに合うハーブを選んで、日常の中で気軽に取り入れてみてはいかがでしょうか。
▼その他の蚊対策と虫除けに関する記事はこちらをチェック▼
蚊対策と虫除けの基本と裏ワザ!夏を快適に過ごす誰でもできる効果的な対策まとめ!
ハーブの虫除けは効果ない?

ハーブを使った虫除けは、自然派志向の方や小さなお子さん・ペットのいるご家庭で人気が高まっています。
ただ、「本当に虫を寄せつけないの?」「市販の虫除けのほうが効くんじゃない?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、ハーブが持つ虫除け効果の根拠や、効果を感じにくい理由、その対策方法、市販の虫除けとの違いまでをわかりやすくご紹介していきます。
ハーブの虫除け効果に科学的根拠はある?
実は、ハーブに虫を遠ざける働きがあることは、いくつかの研究でも確認されています。
レモングラスやシトロネラには「シトロネラール」、ラベンダーには「リナロール」、ペパーミントには「メントール」といった成分が含まれており、これらが虫の嗅覚に影響を与えることで寄ってこなくなるといわれています。
こうした成分を精油(エッセンシャルオイル)として使った実験では、蚊やゴキブリなどに対して忌避効果があったという結果も報告されています。
ただし、鉢植えやドライハーブなど“そのままの状態”で使用すると、成分が空気中にあまり広がらず、効果を感じにくいこともあります。
より実感したい場合は、精油を使ったスプレーやディフューザーなどのアイテムと組み合わせるのがおすすめです。
ハーブ自体に虫を寄せつけにくくする力があるのは確かですが、使い方や場所によって効果に差が出る点は理解しておきましょう。
効果を感じにくい理由とその対策
「ハーブを置いているのに虫が寄ってくる…」そんな経験がある方もいるかもしれません。
実際、ハーブの虫除け効果が実感しにくいケースには、いくつかの理由があります。
香り成分が時間とともに空気中に拡散してしまい、持続力が弱くなること。
また、置く場所の風通しや湿度、気温によっても効果の感じ方が大きく変わります。
さらに、使っているハーブの種類や状態によっても、効果に違いが出やすいです。
乾燥が進んだハーブや香りの弱いものは、十分な効果を発揮しにくいかもしれません。
そんなときは、複数のハーブを組み合わせて使ったり、こまめに取り替えたりするのがおすすめ。
また、エッセンシャルオイルを使ってアロマディフューザーや虫除けスプレーとして活用するのも効果的です。
こうした工夫を加えることで、ハーブの虫除け効果をよりしっかりと感じられるようになります。
市販の虫除け剤との違い
ハーブと市販の虫除け剤を比べると、違いがはっきりと見えてきます。
市販の虫除け剤には、ディートやイカリジンなどの化学成分が配合されており、これらは高い虫除け効果と長い持続時間が特徴です。
アウトドアや虫の多い場所では、その即効性と頼もしさが大きなメリットといえます。
一方で、ハーブは自然由来の香り成分を活かして虫を寄せつけにくくするため、肌や環境にやさしい点がポイントです。
ナチュラルな生活を意識したい方や、赤ちゃん・ペットがいるご家庭では、安心感を求めてハーブを取り入れるケースも少なくありません。
ただし、ハーブの虫除けはどうしても持続時間が短めで、環境によって効果のばらつきが出ることもあります。
そのため、どちらを選ぶかは使用する場面や目的次第。
外出時や効果を重視したい場合は市販品、日常的な予防や香りを楽しみながら使いたいときにはハーブと、シーンに応じて使い分けるのがおすすめです。
ハーブに虫が寄ってくることも?

虫除けにぴったりというイメージのあるハーブですが、実は育てていると虫が寄ってくることもあるんです。
特に家庭菜園やプランターで育てていると、知らない間に葉が食べられていたり、小さな虫がついていたりすることも。
ハーブを元気に育てるには、どんな虫がつきやすいのかを知っておくことが大切です。
ここでは、ハーブに寄りやすい虫の種類や、その対策、毎日のケアのコツについて詳しく解説していきます。
ハーブに集まる虫の種類
ハーブのまわりには、意外といろいろな虫が集まります。
よく見られるのは、アブラムシ、ハダニ、ナメクジ、アオムシ、ヨトウムシなどです。
たとえばアブラムシは、カモミールやバジルの新芽に寄ってきやすく、植物の栄養を吸い取ることで生育に影響を与えることがあります。
ハダニは葉の裏に発生しやすく、葉の色が悪くなったり、カサカサになったりする原因になります。
ナメクジやカタツムリは湿った環境を好み、夜間に活動してワイルドストロベリーやバジルのやわらかい葉を食べてしまうことも。
アオムシやヨトウムシも葉をむしゃむしゃ食べるため、放っておくと株全体が弱ってしまうおそれがあります。
特にバジルやルッコラといった葉がやわらかい種類は被害が目立ちやすいです。
どの虫がつきやすいかは、育てているハーブの種類や置き場所、気候によっても変わるため、こまめな観察が欠かせません。
虫が寄る原因と対策
「どうして虫が寄ってくるの?」と疑問に思う方も多いかもしれませんが、実は栽培環境や日々の管理が大きく関係しています。
風通しが悪かったり湿度が高かったりすると、虫たちにとって居心地の良い環境になってしまい、アブラムシやハダニ、ナメクジなどが発生しやすくなります。
また、株が密集していると虫が隠れやすくなり、被害に気づきにくいという面もあります。
このような状況を防ぐには、まず日当たりと風通しの良い場所で育てることが大切です。
さらに、こまめに葉を間引いたり、収穫したりして、光と風が株の奥まで届くようにしましょう。
葉の裏や茎、株元などを定期的にチェックし、虫がいたら早めに取り除くことも重要です。
水や肥料の与えすぎは植物を弱らせるだけでなく、虫が好む環境を作ってしまうので注意が必要です。
化学的な対策に頼らず、手で取り除く・トラップを使うなど自然に配慮した方法もおすすめです。
ハーブの健康を守るポイント
ハーブを元気に育てるために一番大切なのは、やはり日々のちょっとした観察とお手入れです。
毎日葉の色や形、茎や株元の様子をじっくり見て、変色や虫食いの跡、葉の裏に小さな虫や糸のようなものがないかチェックしてみましょう。
少しでも異変に気づいたら、早めに被害のある部分を取り除いて、虫の発生源を取り除くのがポイントです。
水やりは「土がしっかり乾いてから」が基本。
常に湿っていると根腐れや虫の発生を招きやすくなるので注意しましょう。
また、必要に応じて剪定や収穫をして株が蒸れないようにすることも、病害虫の予防になります。
土の状態も重要で、水はけの良い環境を整えるとハーブの根がしっかりと張りやすくなり、丈夫に育ちます。
こうした小さな積み重ねが、ハーブを健やかに保ち、虫に負けない元気な状態をキープするコツです。
虫除けハーブは置くだけでいい?

「虫除けハーブって、ただ部屋やベランダに置くだけで効果があるの?」と気になっている方は多いのではないでしょうか。
確かにハーブには虫が苦手とする香り成分が含まれていますが、置き方や使い方によってその働きには差が出ることも。
ここでは、虫除けハーブの効果的な置き方や香りの広げ方、そして香りを長く保つための工夫について、わかりやすくご紹介します。
ハーブの置き方と効果の関係
虫除けハーブは、ただなんとなく置くだけでは効果を実感しづらいことがあります。
ハーブに含まれる香り成分は、虫が嫌がるとされるものが多く、空気中にしっかりと広がることで虫が寄りにくい空間を作りやすくなります。
ラベンダーやペパーミント、レモングラスなどは、特に香りが強い種類として知られており、虫を遠ざける目的で使われることもあります。
ただし、鉢植えやポットに入れて部屋の片隅に置いているだけでは、香りがあまり広がらず、十分な効果が感じられないこともあります。
虫が入りやすい窓辺や玄関、ベランダの出入口など、風通しがよくて香りが届きやすい場所に設置すると、より効果が発揮されやすくなります。
また、同じ場所に長く置きっぱなしにするよりも、状況に応じて置き場所を変えてみるのもおすすめです。
ハーブの香りが届く範囲を意識して置くことで、虫が寄りにくい空間づくりにつながります。
香りの拡散方法と持続性
虫除けハーブの香りは、時間が経つにつれて少しずつ弱まっていきます。
特に生のハーブをそのまま置いた場合、香りの広がりや持続力には限界があります。
より長く香りを楽しみたい場合には、ドライハーブやポプリ、精油(エッセンシャルオイル)を活用するのがおすすめです。
ドライハーブを布の小袋に入れて吊るしたり、玄関や窓辺に飾るだけでも、やさしい香りが空間にふんわり広がります。
エッセンシャルオイルを使ってアロマディフューザーやスプレーを活用すれば、短時間で香りを部屋中に広げることができるので、手軽さと持続性の両方を求める方にぴったりです。
また、生の葉を軽く揉むだけでも香りが強くなり、虫が寄りにくい状態を作りやすくなります。
定期的にハーブを交換するなど、少しの工夫で香りの効果を持続させることができます。
効果を高めるための工夫
虫除けハーブの効果をよりしっかりと実感したい場合は、いくつかの工夫を取り入れてみましょう。
ラベンダー、ゼラニウム、ミント、レモングラスなど複数のハーブを組み合わせることで、香りにバリエーションが出て、より虫が寄りにくい環境を作りやすくなります。
それぞれのハーブには独自の香り成分があり、組み合わせることで香りの幅が広がると同時に、虫が嫌がる要素も増えるといわれています。
香りが弱くなってきたと感じたときは、新鮮なハーブに交換するだけでなく、葉を軽く揉んで香りを引き出すのも効果的です。
さらに、香りを広げたい場所に応じて使い方を変えるのもポイント。
室内ではディフューザーやポプリ、玄関やベランダでは小さな鉢植えやドライハーブの吊り下げなど、空間に合わせた工夫を取り入れると、ハーブの香りが活かされやすくなります。
ちょっとしたアイデアを加えることで、虫が気になりにくく、心地よい空間をつくることができます。
虫除けハーブで玄関に置くなら?

玄関は外とつながっているため、虫が入り込みやすい場所のひとつです。
とはいえ、強い成分を含む虫除けアイテムを使うのに抵抗がある方も多いのではないでしょうか。
そんなとき、ハーブを使ったナチュラルな虫対策が注目されています。
見た目も香りも楽しめるハーブは、インテリア感覚で置けるのが魅力。
ここでは、玄関にぴったりなハーブの種類や効果的な置き方、香りの持続性を高めるコツなどをご紹介します。
玄関におすすめのハーブ種類
玄関に置く虫除け対策用のハーブとして人気があるのは、ペパーミント、ラベンダー、ローズマリー、ゼラニウム、レモングラス、シトロネラ、ユーカリ、そしてカレンソウなどです。
これらのハーブは、それぞれ独自の香り成分を持っており、虫が寄りつきにくいといわれています。
特にペパーミントやラベンダーは爽やかな香りでリラックス効果も期待でき、育てやすさもポイントです。
ゼラニウムやレモングラスは香りが強めで、玄関先に置くとフレッシュな雰囲気を演出してくれます。
ローズマリーは料理にも使えるうえに見た目もスタイリッシュ。
ユーカリやシトロネラは葉に清涼感のある香りがあり、夏の玄関まわりにぴったりです。
どのハーブも香りや育てやすさに違いがあるので、ご家庭の玄関の環境(日当たり・風通しなど)や自分の好みに合わせて選ぶことが大切です。
置き方・アレンジ例
ハーブは鉢植えやプランターにして玄関先に置くのが一般的ですが、ちょっとした工夫でインテリアとしても楽しめます。
数種類のハーブを寄せ植えにすれば、香りに奥行きが出るうえ、見た目にも華やかになります。
スペースが限られている場合は、小さめの鉢を数個並べたり、吊るして飾れるハンギングプランターを活用するのもおすすめです。
さらに、ドライハーブを使ったサシェ(香り袋)を作って玄関の棚やドアノブに吊るす方法も人気があります。
香りを楽しみつつ、ナチュラルでおしゃれな印象を与えることができます。
ハーブの葉は定期的に摘み取って整えると見た目もすっきりし、香りも新鮮な状態を保ちやすくなります。
忙しい方でも無理なく続けられるよう、水やりの頻度や日当たりなど、お世話がラクな品種を選ぶのもポイントです。
玄関での虫除け効果を高めるポイント
ハーブを玄関に置くなら、できるだけ効果を引き出せるように配置やお手入れに工夫をしましょう。
まず、香りがしっかり広がるように、玄関の出入り口近くや風通しの良い場所に設置するのがおすすめです。
香り成分は空気にのって拡散されるため、閉ざされた空間より風の通り道に置いた方が広がりやすくなります。
また、複数のハーブを組み合わせることで、異なる香り成分が重なり合い、虫が嫌がる環境をつくりやすくなります。
ドライハーブを小袋に入れたり、エッセンシャルオイルを含ませたディフューザーを併用するのも、香りを長持ちさせるうえで効果的です。
時間が経って香りが薄くなったと感じたら、新しい葉に交換したり、葉を軽く揉んで香りを強めてみてください。
日々の手入れとしては、葉の状態を観察し、変色や傷みがあれば早めに取り除くこと。
ハーブが元気であれば、香りもしっかり感じられますし、虫が好みにくい環境を保ちやすくなります。
こうしたちょっとした気配りが、快適で虫の少ない玄関づくりにつながります。
虫除けハーブで最強の庭で育てるなら?

庭にハーブを植えると、見た目が華やかになるだけでなく、香りでも癒やされますよね。
さらに、虫が寄りにくいとされるハーブを選べば、ナチュラルな虫対策としても活躍します。
ここでは、庭植えに向いている虫除けハーブの種類や、育てやすさ・手入れのコツ、虫が寄りにくくなるハーブの配置方法まで、ガーデニング初心者の方でも実践しやすい情報をわかりやすくご紹介します。
庭植えに適した虫除けハーブ
庭で虫除けとして活用しやすいハーブには、香りがしっかりと感じられるものが多くあります。
特に人気なのは、ペパーミント、ラベンダー、ローズマリー、タイム、ゼラニウム、レモングラス、シトロネラ、バジル、ユーカリ、カレンソウ、カモミールなどです。
これらのハーブは、それぞれ異なる香りを持ち、庭のアクセントにもなります。
ラベンダーやローズマリーのような多年草は、一度植えると長く楽しめるのが魅力です。
タイムやミントはグランドカバーとして広がりやすく、雑草対策にもなります。
ただし、ミントは繁殖力がとても強いため、他の植物との距離や植える場所に注意が必要です。
レモングラスやシトロネラは背が高く育つので、目隠しや庭の仕切りとして活用するのもおすすめです。
自分の庭の広さや日当たり具合、好きな香りを基準に選んでみてください。
育てやすさとメンテナンス方法
虫除け効果を期待しながらハーブをしっかり育てるには、日々の管理が重要です。
ラベンダーやローズマリーは乾燥に強く、日当たりと風通しが良い場所を好みます。
水はけの良い土に植えることで根腐れを防ぎ、元気に育ちやすくなります。
ミントやタイムはとても丈夫ですが、植えっぱなしにすると広がりすぎてしまうこともあるので、花壇の縁や鉢植えで管理すると安心です。
レモングラスやシトロネラなど熱帯原産のハーブは、寒さに弱いため冬場は鉢に植え替えて室内に移すことも考えましょう。
また、風通しを保つために定期的な剪定も欠かせません。
葉が密集しすぎると蒸れてしまい、健康な育成の妨げになります。
肥料は生育期に少し与える程度でOK。
水のやりすぎや過湿を避ければ、病害虫の発生も抑えやすくなります。
こうしたポイントを押さえるだけで、初心者でも育てやすく、手間も少なくて済みますよ。
庭全体の虫除け効果を高める配置
庭にハーブを植える際は、ただ並べるのではなく、効果的な配置を意識することで虫除けとしての役割をより感じやすくなります。
ポイントは「香りが広がる場所」に置くことです。
玄関前やテラスまわり、窓の近く、小道の両脇など、人がよく通る場所にハーブを植えると、香りを楽しみながら虫対策にもつながります。
さらに、香りの異なる複数のハーブを組み合わせて植えることで、空間全体に香りが広がりやすくなり、虫が寄りにくい環境を作りやすくなります。
地面に広がるように植えるミントやタイムは、下からの侵入を防ぐイメージで活用できます。
反対にレモングラスやシトロネラは縦に伸びるので、目隠しや仕切りのような使い方もできて便利です。
見た目と機能の両方を考えながら配置すると、庭全体がより快適な空間になります。
虫除けハーブで最強のゴキブリに効果があるのは?

ゴキブリをできるだけ自然な方法で遠ざけたいと考える方にとって、ハーブの活用は気になる対策法のひとつです。
特に、化学成分を避けたい方や小さなお子さん、ペットがいるご家庭では、ナチュラルなアプローチが注目されています。
ここでは、ゴキブリが苦手とする香りを持つとされるハーブの種類や効果的な使い方、他の虫への応用方法まで、わかりやすく解説していきます。
ゴキブリに効果が期待できるハーブ
ゴキブリは特定の香りを嫌う性質があるとされており、その点を活かしてハーブを取り入れる方も増えています。
中でも知られているのが、スペアミント、日本ハッカ、クローブ、レモングラス、ベチバー、キャラウェイ、アロマティカス、ジョチュウギク(除虫菊)などです。
これらのハーブに共通しているのは、独特な強い香り成分を含んでいることです。
ミント系はメントールの爽やかな香りが特徴で、ゴキブリが近寄りにくいとされています。
クローブに含まれるオイゲノールも香りが強く、スパイスとしての用途だけでなく、虫が寄りつきにくい香りとしても知られています。
また、ベチバーやキャラウェイは独特の土っぽい香りがあり、組み合わせて使うことで香りのバリエーションが広がります。
なお、ユーカリは一部でゴキブリを引き寄せる可能性があるという説もあるため、使用は様子を見ながらがおすすめです。
ハーブの種類ごとに香りの強さや広がり方が異なるため、何種類かを併用して様子を見るのも良い方法です。
効果的な使い方と注意点
ハーブを活用する際は、香りをしっかり広げられる方法を選ぶことがポイントです。
エッセンシャルオイルを使う場合は、コットンやお茶パックに数滴たらして、キッチンの隅やシンク下、玄関、換気扇まわりなど、ゴキブリが出やすい場所に置いておきます。
また、水で薄めてスプレーにし、定期的に噴霧することで香りを持続させるのもおすすめです。
乾燥ハーブを使う場合は、サシェ(香り袋)にして棚や収納の中に設置すると手軽に取り入れられます。
いずれの方法も、香りが薄れてきたらこまめに交換することが大切です。
ハーブはあくまでも「寄せつけにくくする」ためのサポートアイテムであり、駆除や殺虫を目的としたものではありません。
そのため、効果の感じ方には個人差があります。
また、ペットや小さなお子さんがいるご家庭では、誤って口にしないよう設置場所に配慮することも忘れずに。
香りの拡散具合や持続時間は、気温や湿度、空気の流れによっても変わるため、適宜調整しながら使用するのがコツです。
他の虫への応用例
ゴキブリを遠ざける目的で使われるハーブの中には、他の虫にも応用できるものがあります。
ミントやレモングラス、ラベンダー、タイムなどは、蚊やハエ、アリといった日常的に気になる虫に対しても香りでアプローチしやすいとされています。
クローブやローズマリーも衣類の防虫やキッチン周辺での活用例があり、使い方次第で幅広く対応できるのが魅力です。
ただし、すべての虫が同じ香りを嫌がるわけではなく、種類によって反応に差があることは覚えておきましょう。
そのため、複数のハーブを組み合わせて使用することで、より多くの虫に対応できる可能性があります。
天然由来の対策を試してみたい方は、自分の目的に合ったハーブを選び、生活の中に無理なく取り入れてみるとよいでしょう。
自然な香りを楽しみながら、虫の気になりにくい空間をつくるヒントになります。
虫除けハーブで最強はかれんそう?
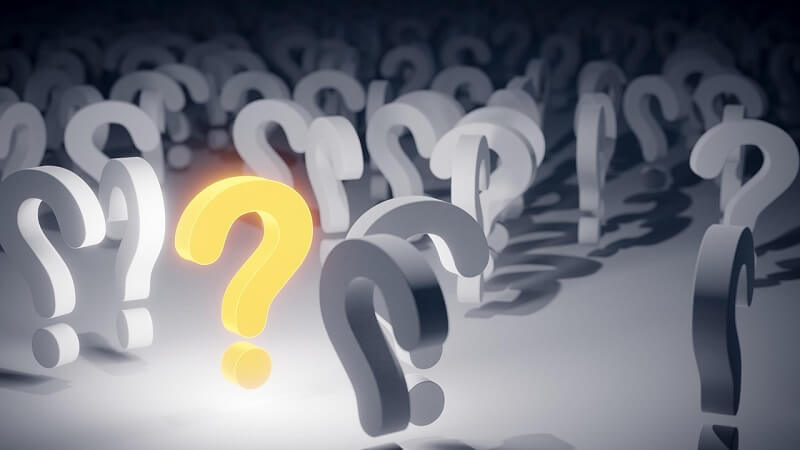
虫除け対策として、見た目も香りも楽しめる「蚊連草(かれんそう)」が注目を集めています。
特にナチュラルな方法で蚊などの虫を寄せつきにくくしたいという方にとっては、気になる存在ではないでしょうか。
ここでは、蚊連草の特徴や他のハーブとの違い、育て方や活用のコツまで、分かりやすくご紹介します。
かれんそう(蚊連草)の特徴と効果
蚊連草は、ゼラニウムの仲間で見た目が美しく、爽やかな香りがするのが特徴です。
特に、シトロネラールやシトロネロールといった成分が含まれており、これらの香りは蚊が苦手とされていることから、ガーデニングや虫対策に取り入れる方が増えています。
葉に触れるとフレッシュな香りが広がるため、ベランダや玄関などに置いて楽しむ人も多いです。
ただし、蚊連草には「殺虫」や「駆除」のような効果はなく、あくまで香りによって虫が近づきにくい空間づくりをサポートする役割です。
鉢植えやプランターでも育てやすく、日当たりと風通しのよい場所を選べば、比較的手間もかかりません。
見た目が華やかなので、インテリアグリーンとしてもおすすめです。
他のハーブとの比較
虫除けに使われるハーブは蚊連草だけではありません。
レモングラスやシトロネラ、ラベンダー、ミント、バジルなども虫が寄りにくいとされる香り成分を持っており、それぞれ特徴があります。
レモングラスやシトロネラは柑橘系のさっぱりとした香りが強く、香りの持続性にも定評があります。
ラベンダーやミントは育てやすく、優しい香りが人気です。
バジルは料理にも使えるうえ、虫が好まない香りを持っている点でも便利です。
これらのハーブは、単体でも使えますが、複数を組み合わせると香りのバリエーションが広がり、より虫が寄りつきにくい環境づくりに役立ちます。
香りの好みや育てやすさ、使う場所の雰囲気に合わせて選ぶのがポイントです。
かれんそうの活用方法
蚊連草は、ガーデニング初心者でも扱いやすく、鉢植えやプランターで育てて、ベランダや玄関、リビングの窓辺など、いろいろな場所で楽しめます。
葉を軽くなでたり剪定したりすると、香りが強く感じられるようになるので、香りを効果的に広げたいときにおすすめです。
また、切り取った葉を乾燥させてサシェ(香り袋)にしたり、リースやポプリとして飾る方法も人気があります。
おしゃれに楽しみながら、虫が寄りにくい環境づくりをサポートできるのが魅力です。
育てる際は、水やりのタイミングや風通し、日当たりに注意することで、長く元気に香りを楽しめます。
蚊連草は「ナチュラルな虫対策」として、見た目と機能の両方を重視したい方にぴったりのハーブです。
ハーブの虫除けは効果ないに関するまとめ
ハーブの虫除けについては「本当に効くの?」と疑問を持つ方も多いかもしれません。
たしかに、ハーブには殺虫や完全に虫を駆除するような強い作用があるわけではありませんが、ミントやレモングラス、蚊連草(かれんそう)、ラベンダーなどのハーブには、虫が苦手とする香り成分が含まれており、それによって虫が寄りつきにくい環境をつくることが期待できます。
とはいえ、ハーブの虫除け効果は「補助的なもの」という位置づけで考えておくのがポイントです。
香りの広がり方や強さは、ハーブの種類や設置場所、育て方によって大きく変わってきます。
香りが弱くなってきたら葉を軽く揉んだり、新しい葉に取り替えるなど、こまめなケアも大切です。
また、複数のハーブを組み合わせて使うことで、より広範囲に香りを広げることができます。
ペットや小さなお子さんがいるご家庭では、ハーブの種類や設置場所にも気を配りましょう。
誤って口にしないように工夫したり、アレルギーの心配がないかを確認することも忘れずに。
市販の虫除けアイテムと比べると即効性や持続力は控えめかもしれませんが、ハーブの魅力はなんといっても自然で安心感があるところ。
香りを楽しみながら、ナチュラルに虫を寄せにくい空間を作れるのは嬉しいポイントです。
まずは育てやすいハーブから気軽に取り入れて、自分の暮らしに合った方法で楽しんでみてくださいね。
▼その他の蚊対策と虫除けに関する記事はこちらをチェック▼
蚊対策と虫除けの基本と裏ワザ!夏を快適に過ごす誰でもできる効果的な対策まとめ!

