
エアコンの送風で湿度が上がると感じたことはありませんか?
梅雨や夏場など、湿気が多い時期には特に悩まされがちです。
せっかくエアコンを使っているのに、部屋の湿気がすごくて快適じゃない、送風モードにしているのに湿度が上がる、さらにはカビが心配という方も多いのではないでしょうか。
寝るときにもその悩みが出て、除湿したはずなのに湿度が下がらず、結局寝苦しく感じてしまうこともあります。
実は、エアコンの送風モードは空気を循環させるだけで、温度や湿度を下げる効果はありません。
冷房や除湿運転後、エアコン内部に残った水分が送風運転で室内に戻ることが、湿度が上がる原因のひとつです。
この現象を「湿度戻り」や「湿気戻り」と呼び、特に冷房が止まるとき(サーモオフ)に発生しやすいです。
さらに、エアコンの設定温度や風量の調整がうまくいかないと、サーモオフによって送風が頻繁に切り替わり、湿度が上がる原因になります。
湿度をうまくコントロールするためには、除湿モードを活用したり、温度を少し低めに設定したり、風量を調整することが大切です。
定期的なエアコンの掃除も効果的です。
カビを防ぎ、快適な睡眠環境を作るためにも、エアコンの使い方を見直すことが大切です。
湿度や送風の悩みを解決し、快適な空間を作るために、この記事で正しい知識と対策を学びましょう。
▼その他の梅雨の湿度対策に関する記事はこちらをチェック▼
梅雨の湿度対策で快適な部屋づくり!部屋干しも安心のカビや臭いを防ぐテクニックまとめ
エアコンの送風で湿度が上がる理由
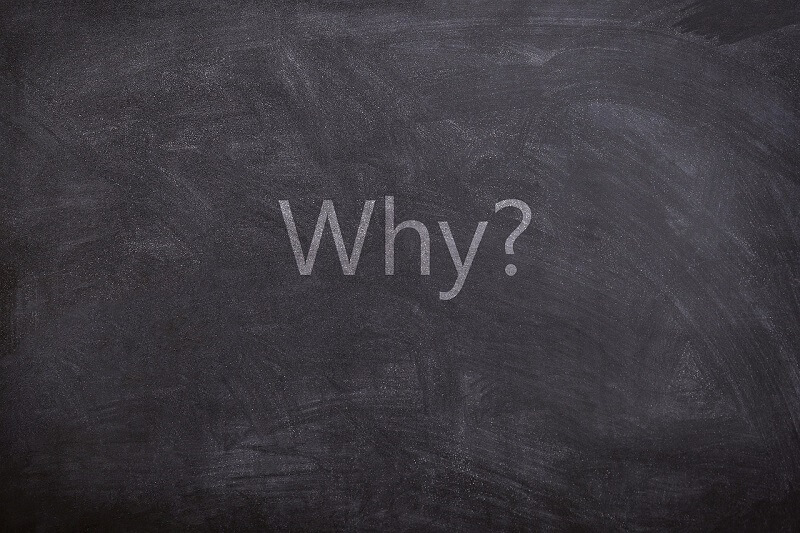
「エアコンの送風って空気を乾燥させるんじゃないの?」と思っている方もいるかもしれません。
でも実は、送風モードを使っていると、かえって湿度が高く感じられることがあるんです。
特にジメジメしやすい梅雨や蒸し暑い夏は、ちょっとした湿度の変化にも敏感になりますよね。
ここでは、送風モードの基本的な仕組みや、エアコン内部に残った水分による「湿度戻り」、そして温度差と湿度の関係について、わかりやすく解説していきます。
送風モードの仕組みと湿度の関係
エアコンの送風モードは、名前の通り「風を送る」だけの機能です。
冷房や暖房のように空気を冷やしたり温めたりはしないため、室温そのものを変えることはありません。
そして当然、空気中の水分を取り除いたり加えたりすることもないのが特徴です。
それでも「送風モードを使っていると、なんだか湿度が高くなる気がする」という声は少なくありません。
その理由のひとつが、エアコン内部に残っている水分です。
エアコンは冷房運転をしているとき、内部で結露が発生して水がたまることがあります。
この水分が完全に乾かないまま送風モードに切り替わると、風と一緒にその湿気が室内に戻ってしまうことがあるのです。
つまり、送風モード自体が湿度を上げているわけではありませんが、エアコン内部に残った水分の影響で、体感として湿度が高く感じられることがあります。
湿度管理をしっかり行いたい場合は、除湿モードや冷房モードをうまく使うのがおすすめです。
サーモオフ時に発生する湿度戻りとは
冷房を使っているとき、設定した温度まで部屋が冷えると、エアコンは自動的に冷房運転を一時停止し、送風だけの運転に切り替わることがあります。
この状態を「サーモオフ」といいます。
エアコンが設定温度をキープしようとして行う通常の動作です。
しかしこのタイミングで、内部にたまっていた結露水が乾ききらずに残っていると、送風によってその湿気が再び室内に戻ってしまうことがあります。
これが「湿度戻り」と呼ばれる現象です。
突然ムワッとした空気を感じるのは、まさにこの湿気の影響かもしれません。
この湿度戻りはエアコンの故障ではなく、ごく自然な働きのひとつです。
ただし、頻繁に蒸し暑さを感じる場合や、エアコンの効きが悪くなったと感じたときには、フィルターの汚れや内部のカビ、ドレンホースの詰まりなどが原因の可能性もあるため、専門業者に点検してもらうと安心です。
快適な空気環境を保つには、定期的なお手入れも大切ですね。
室内外の温度差と湿度上昇のメカニズム
部屋の湿度は、単純に水分の量だけでなく「温度」にも大きく左右されます。
空気は温度が高いほど多くの水分を含むことができ、逆に冷えると含める水分量が減るため、同じ水分量でも湿度が上がったように感じるのです。
冷房を使って室温が下がった場合、水蒸気の量は変わっていなくても相対湿度が上昇することがあります。
一方で、送風モードに切り替わって室温が上がると、空気の中の水分量に変化がなくても相対湿度は下がる方向に向かいます。
しかし、先述の通りエアコン内部に残っている水分が送風と一緒に放出されると、実際に空気中の水分量が増えてしまい、湿度が上がることもあります。
このように、室内外の温度差やエアコンの運転状態によって、湿度は日々変動します。
温度と湿度の関係を理解しておくと、エアコンの設定を上手にコントロールしながら、より快適な空間づくりができますよ。
エアコンの湿度戻り対策!

エアコンを使っているのに、いつの間にか湿度が上がってムシムシ…。
そんな「湿度戻り」に悩んだことはありませんか?せっかく快適な室温になっても、湿度が高くなると不快に感じることも。
ここでは、湿度戻りを防ぐためのエアコンの賢い使い方や、毎日のメンテナンスのポイント、さらにサーキュレーターや除湿機の上手な活用法をご紹介します。
効果的なエアコンの使い方
湿度戻りをできるだけ防ぐには、エアコンの運転モードや設定温度の工夫がポイントです。
冷房中に設定温度が高すぎると、部屋の温度がすぐに目標に達してエアコンが冷房を止め、送風に切り替わります。
この切り替え時に、エアコン内部に残った水分が空気中に流れ出して、湿度が上がる原因になります。
そのため、冷房の設定温度は少し低めにして、できるだけ冷房が続くようにしてみましょう。
また、除湿(ドライ)モードを活用するのもおすすめです。
除湿モードには「弱冷房除湿」と「再熱除湿」の2種類があり、特に再熱除湿は、室温を下げすぎずに湿度を調整できる仕組みになっています。
これを使えば、寒くなりすぎずに湿度を下げられるので、快適さをキープしやすくなります。
エアコンの機能を上手に使い分けることで、湿度戻りを防ぎながら快適な空間をつくることができます。
メーカーの取扱説明書や公式サイトも参考にすると、自宅のエアコンに合った使い方がわかりやすくなりますよ。
定期的なフィルター掃除とメンテナンス
エアコンが本来の性能を発揮するには、こまめなお手入れが欠かせません。
特に、フィルターがほこりで目詰まりしていると、空気の流れが悪くなり、冷房や除湿の効果が落ちてしまいます。
その結果、室温や湿度が思うようにコントロールできず、湿度戻りが起こりやすくなることもあります。
フィルター掃除は2週間に1回を目安に行うのが理想です。
掃除の仕方は簡単で、フィルターを外して水洗いし、しっかり乾かしてから戻すだけ。
これだけでもエアコンの効率がグッと上がります。
エアコン内部にカビや汚れが気になる場合は、専門のクリーニング業者に依頼するのもひとつの方法です。
定期的な掃除を習慣にすることで、エアコンの除湿力をしっかり引き出すことができ、湿度戻りのリスクも減らせます。
エアコンを長持ちさせる意味でも、メンテナンスはとても大事なポイントです。
サーキュレーターや除湿機の併用方法
エアコンだけでは湿度コントロールが難しいと感じたときは、サーキュレーターや除湿機を組み合わせて使うのがおすすめです。
サーキュレーターは、部屋の空気を循環させることで冷たい空気を部屋全体に行き渡らせ、エアコンの効率を高める役割があります。
一方、除湿機は空気中の湿気を直接取り除いてくれるアイテムです。
エアコンの除湿機能と一緒に使えば、より早く快適な湿度に近づけやすくなります。
サーキュレーターは部屋の隅や洗濯物の近くに置くと、湿気がこもりにくくなり、カビ対策としても効果が期待できます。
これらのアイテムを上手に使うことで、湿度戻りの予防はもちろん、部屋干しや梅雨時期のジメジメ対策にもなります。
最近はコンパクトで静音設計のものも多く、寝室やリビングにも使いやすいですよ。
エアコンと併用することで、より快適で快眠しやすい環境づくりがしやすくなります。
エアコンの除湿で湿度が上がる?

エアコンの除湿モードを使っているのに、なぜか湿度計の数値が上がっていて「ちゃんと除湿できてるの?」と感じたことはありませんか?
実はこれ、よくある現象なんです。
ここでは、エアコンの除湿の仕組みや、弱冷房除湿と再熱除湿の違い、除湿中に湿度が上がってしまう理由とその対策について、わかりやすくご紹介します。
除湿モードの動作原理
エアコンの除湿モードは、室内の空気を取り込んで冷やすことで水分を取り除き、乾いた空気を戻すという流れで湿度を下げます。
内部の熱交換器に空気を通すことで、空気中の水分が水滴となって取り除かれ、結果的に部屋の湿度が下がる仕組みです。
冷房に似た動きをしますが、除湿モードでは冷やしすぎないように温度のコントロールが加わるのが特徴です。
梅雨時や夏のじめじめが気になる季節には、除湿モードを上手に活用することで、快適な空間をキープしやすくなります。
冷房では寒くなりすぎてしまうという方にとっても、除湿モードはちょうどいい湿度管理の手段です。
エアコンの基本的な機能を知っておくことで、より効率的な使い方ができるようになります。
弱冷房除湿と再熱除湿の違い
エアコンの除湿には「弱冷房除湿」と「再熱除湿」の2つのタイプがあります。
名前だけでは違いがわかりづらいかもしれませんが、それぞれ特長がはっきりしています。
弱冷房除湿は、冷房のように空気を冷やして水分を取り除く方法で、湿度と一緒に室温も下がります。
そのため、長時間使っていると「なんだか寒い」と感じることがあります。
一方で、再熱除湿は冷やして水分を取った空気を再びあたためてから室内に戻す仕組みです。
室温をほとんど下げずに湿度だけを調整できるので、より快適さを感じやすいのがメリットです。
ただし、再熱除湿は電気代がやや高くなる傾向もあるため、季節や体感に応じてモードを使い分けるのがおすすめです。
たとえば、暑さが気にならない雨の日には再熱除湿、真夏の蒸し暑い日は弱冷房除湿、といった使い分けが快適さと省エネの両立につながります。
除湿運転中に湿度が上がるケースと対策
「除湿モードにしてるのに湿度計の数字が上がってる…」そんなときでも、エアコンがちゃんと働いていないとは限りません。
実はこれは「相対湿度」と「室温」の関係によるものかもしれません。
湿度計が表示するのは「相対湿度」といって、空気がどれくらい水分を含んでいるかの割合です。
除湿で室温が下がると、空気が持てる水分の量も減るため、結果的に相対湿度が上がってしまうことがあります。
つまり、実際には空気中の水分が減っているのに、湿度計では高めの数字が出てしまうというわけです。
また、フィルターが汚れていたり、エアコン内部の冷媒ガスが不足していたりすると、除湿機能がうまく働かないこともあります。
こうした場合は、フィルターをこまめに掃除したり、年に1回ほどの点検を受けたりすることで、エアコンの機能をしっかりキープできます。
それでも冷たい風が出ない、湿度がなかなか下がらないといった症状がある場合は、早めに専門業者へ相談することをおすすめします。
正しい対策を知っておくことで、ムダな電気代やストレスを減らし、快適な空間を保ちやすくなります。
エアコンの湿気がすごい理由と対策

「エアコンをつけているのに部屋がなんだかジメジメしている…」そんな悩みを抱えている方は意外と多いです。
湿気がたまると空気が重たく感じたり、カビの原因になったりと、不快な環境になりがちですよね。
ここでは、エアコン使用時に湿度が高くなりやすい理由や、その対策方法をわかりやすくご紹介します。
次のセクションでは、まずエアコン内部のカビや汚れと湿気の関係について見ていきましょう。
エアコン内部のカビ・汚れが湿度に与える影響
エアコンの内部が汚れていると、湿気がなかなか取れにくくなることがあります。
特に冷房や除湿運転をしたときには、内部の熱交換器やドレンパンに結露が発生しやすく、水分がたまりやすい状態になります。
この水分がホコリと混ざると、カビが好む環境ができあがってしまうのです。
カビが発生したままのエアコンを使うと、風と一緒にイヤなにおいが広がったり、空気の質が気になったりすることも。
また、カビの存在によって空気の流れが悪くなると、除湿機能がうまく働かなくなることもあるため、室内の湿度が下がりにくくなってしまいます。
こういったトラブルを防ぐには、フィルターを2週間に1回程度のペースでこまめに掃除するのがおすすめです。
さらに、内部のカビや汚れが気になる場合は、プロのエアコンクリーニングを検討するのもひとつの方法です。
清潔なエアコンを保つことは、快適な室内環境づくりの第一歩です。
部屋の換気不足と湿度の関係
エアコンを使うときは窓を閉め切ることが多いため、どうしても換気不足になりがちです。
特に長時間エアコンを使用していると、室内の空気が滞って湿気がたまりやすくなります。
この状態が続くと、ジメジメ感が増すだけでなく、カビのリスクも高まるため注意が必要です。
さらに梅雨や夏場は、外の空気自体に湿気が多いため、窓を開けるタイミングや換気の工夫も大切になってきます。
湿度が比較的低い朝や夜に短時間だけ窓を開ける、または換気扇を併用することで、効率よく湿気を逃がすことができます。
また、サーキュレーターや扇風機を使って部屋の空気を動かすと、空気のよどみが解消されて湿度が一箇所にこもるのを防げます。
換気を意識することで、エアコンの除湿機能もよりしっかり働きやすくなりますので、日頃から空気の流れを意識するのがポイントです。
湿気対策に有効な家電やグッズ
湿気対策にはエアコンだけでなく、他の家電や便利グッズを組み合わせるのが効果的です。
特に除湿機は、空気中の水分を直接取り除くことができるので、梅雨時期や夏場の湿度コントロールにとても役立ちます。
エアコンと併用することで、より快適な空間をキープしやすくなります。
また、サーキュレーターや扇風機を使えば、部屋の空気をまんべんなく循環させることができ、湿気が一か所にたまるのを防ぎます。
こうした空気の流れを作る工夫も、湿度対策には欠かせません。
さらに湿度計を置いて、部屋の状態を“見える化”するのもおすすめです。
数値として湿度が確認できると、対策のタイミングもつかみやすくなります。
押し入れやクローゼットといった閉め切った空間には、市販の除湿剤や調湿シートを使うのも効果的です。
これらのグッズをうまく取り入れることで、エアコンの負担を減らしながら、家全体を快適な湿度に保ちやすくなります。
エアコンの送風はカビ予防になる?

エアコンを使っていると「カビが気になる」という声はよく聞かれます。
特に冷房や除湿を使ったあとは、エアコン内部がしっとりしている状態になりがちです。
そんなときに活用したいのが「送風モード」。
内部を乾かしてカビの発生しにくい環境をつくるのに役立つと言われています。
ここでは、送風モードの仕組みや使い方、カビ予防のためにできる日常のお手入れ方法についてわかりやすくご紹介します。
送風運転で内部乾燥する理由
送風運転は、エアコンの中に残った湿気を飛ばすのに効果的な方法です。
冷房や除湿を使ったあと、エアコンの内部、特に熱交換器やドレンパンと呼ばれる部分には結露が発生し、水分がたまりやすくなっています。
この残った水分がそのままだと、カビが発生しやすい状態になります。
そこで送風モードの出番です。
送風運転では冷房のように冷やさず、ただファンを回して風を送るだけなので、内部の湿気を乾かすのに向いています。
空気の流れを作ることで結露した水分を飛ばし、エアコンの中をサラッとした状態に近づけてくれます。
多くのメーカーでは、冷房や除湿の使用後に1〜3時間の送風運転を行うことをおすすめしています。
こまめに送風モードを使うことで、湿気がこもりにくくなり、カビの温床を作らない工夫につながります。
カビ発生を防ぐ送風モードの使い方
送風モードを上手に取り入れることで、エアコンの内部を清潔に保ちやすくなります。
冷房や除湿を使ったあとは、エアコンの中が湿ったままになっていることが多いため、そのままにしておくとカビが発生しやすくなります。
送風モードを使うことで、内部にたまった湿気を乾かし、カビの発生リスクを下げる手助けができます。
使い方のコツとしては、冷房や除湿を切ったあとすぐに送風モードに切り替えるのがポイントです。
1〜4時間程度、送風を続けるのが目安とされています。
最近では「内部クリーン」や「自動乾燥」などの機能がついている機種も増えており、ボタンひとつで送風や乾燥を自動的に行ってくれるタイプもあります。
こうした便利な機能も、取扱説明書を参考にしながら積極的に活用しましょう。
送風モードだけでカビの発生を完全に防ぐことは難しいですが、毎日のちょっとした工夫でカビが繁殖しにくい環境を整えることはできます。
送風モードはその第一歩として取り入れやすい方法なので、ぜひ日常に組み込んでみてください。
エアコンのカビ掃除とメンテナンスのポイント
送風モードでの内部乾燥はとても有効ですが、それだけでは不十分な場合もあります。
カビをしっかり予防するためには、エアコンの内部を定期的に掃除したり、フィルターを清潔に保つことが欠かせません。
まず、フィルターは2週間に1度を目安に掃除するのがおすすめです。
ホコリがたまると、風通しが悪くなって湿気もこもりやすくなりますし、カビの温床にもなりかねません。
また、熱交換器の奥など自分では手が届きにくい部分は、プロのクリーニング業者に依頼するのもひとつの方法です。
専門の道具や洗浄剤を使ってしっかりクリーニングしてもらえるので、安心感があります。
さらに、取扱説明書やメーカーのホームページには、機種ごとのメンテナンス方法が詳しく載っています。
内部乾燥機能の設定方法や、お手入れ時の注意点も確認できるので、使い方に迷ったときはチェックしておくと安心です。
送風モードと定期的な掃除を組み合わせることで、エアコンの中を清潔に保ちやすくなり、快適な空気環境づくりにもつながります。
カビを防ぐには日々の小さな積み重ねが大切です。
エアコンの送風は寝るときにそのままでいい?

寝るとき、エアコンを送風モードのままにしても大丈夫なのか、迷う方は意外と多いのではないでしょうか。
送風モードは冷房に比べて電気代が抑えやすく、体にもやさしい印象がありますが、快適さや体調とのバランスも大切です。
ここでは、就寝時に送風モードを使う際のメリットとデメリット、快眠につながるエアコンの使い方、健康への影響をふまえた注意点について、わかりやすく解説していきます。
就寝時の送風モードのメリット・デメリット
エアコンの送風モードは、冷房や暖房に比べて電力消費が少なく、節電しながら空気を循環させることができます。
体感温度が少しだけ下がることで、冷房だと寒すぎると感じる方にはちょうどよい涼しさを感じられることもあります。
特に夜間、室温がそれほど高くない場合には、やさしい風で快適に感じられることもあるでしょう。
一方で、真夏のように気温や湿度が高い日は、送風だけでは室内が蒸し暑く感じられて寝苦しくなることもあります。
また、送風モードは空気を冷やしたり除湿する働きはないため、室内環境によっては睡眠の質が下がることも。
さらに、風が体に直接当たり続けると冷えすぎの原因にもなるので注意が必要です。
その日の気温や湿度、自分の体調にあわせて送風モードだけで済ませるのか、冷房や除湿と組み合わせて使うのかを判断すると、より快適な夜を過ごしやすくなります。
快適な睡眠環境を保つエアコン設定
快適に眠るためには、エアコンのモードをうまく使い分けるのがポイントです。
寝る1時間くらい前に冷房で部屋をほどよく冷やしておき、その後に送風モードに切り替えると、体が冷えすぎず、スムーズに入眠しやすくなります。
送風モードを使う際は、風量を「弱」に設定し、風が直接体に当たらないように風向きを調整しましょう。
風が当たることで涼しく感じる一方、当たりすぎると寒さを感じて目が覚めてしまうこともあります。
また、湿度が高いと寝苦しさにつながるため、就寝前に除湿モードを短時間だけ使って湿気を軽減するのも効果的です。
最近のエアコンには「快眠モード」や「おやすみタイマー」といった便利な機能が搭載されている機種もあり、こうした機能を活用することで、室温を自動調整しながら心地よい睡眠環境を保ちやすくなります。
自分に合ったモード設定を見つけることで、夏の夜でもぐっすり眠れるようになりますよ。
健康や体調への影響と注意点
送風モードは冷房よりも体に優しいと感じる方が多いですが、長時間風が当たる状態が続くと、体が冷えてしまうことがあります。
特に寝ている間は無意識に冷たい風を浴び続けることになるため、喉が乾燥したり、肩こりやだるさにつながることも。
そのため、送風モードを使うときは、風向きを壁側や天井向きに設定し、直接風が当たらないようにするのがポイントです。
さらに、タイマー機能を活用して、必要な時間だけ稼働させる工夫も有効です。
また、冷え性の方や小さなお子さん、高齢の方がいるご家庭では、寝具やパジャマで体温調節を行うことも大切です。
エアコンの送風モードは便利ですが、体調や環境に合わせて無理なく使うことが大切です。
工夫次第で、暑い夜も快適に過ごせるようになりますよ。
エアコンの送風運転と電気代の関係

エアコンの電気代を少しでも抑えたいときに注目されるのが「送風モード」です。
冷房や暖房に比べて電力消費が少ないため、節電の味方として活用している方も多いでしょう。
ただし、送風モードは温度や湿度を調整するものではなく、あくまで空気を循環させる機能です。
ここでは、送風モードの電力の特徴や、湿度対策とのバランス、上手に節電するコツなどを詳しくご紹介します。
送風モードの消費電力の特徴
エアコンの送風モードは、室内の空気を循環させるだけの機能なので、消費電力が非常に少ないのが大きなメリットです。
冷房や暖房を使うと、室外機が稼働して電力消費が1,000W以上になることもありますが、送風モードの場合はその心配がありません。
一般的には15W〜20Wほどの電力で運転できるため、1時間あたりの電気代はわずか0.5円前後と言われています。
例えば、毎晩8時間使っても1か月で120円程度と、とても経済的です。
扇風機と同じくらい、あるいはそれより少ない電力で使えることもあるため、「とにかく電気代を抑えたい」という方にはおすすめの運転方法です。
家電メーカーや電力会社の節電情報でも、省エネ対策として送風モードが取り上げられることが多くなっています。
湿度対策と電気代節約のバランス
送風モードは電気代が抑えられる一方で、湿度や気温を下げる力はありません。
そのため、真夏の蒸し暑い日などは、送風だけでは物足りなく感じることがあります。
特に湿度が高いと、体感温度も上がり、寝苦しさを感じる原因になることもあります。
そんなときは、まず冷房や除湿モードで部屋をある程度快適な状態にしておき、その後に送風モードへ切り替えるのがおすすめです。
これにより冷房や除湿の稼働時間を減らしつつ、室内の空気をうまく循環させて過ごしやすい環境を維持できます。
また、夜間や外気温が比較的低い時期には、送風モードでも十分に快適に過ごせることがあります。
節電を意識しつつ、湿度や気温の変化に合わせて柔軟にモードを使い分けることが、快適さと節約の両立につながります。
効果的な節電テクニックと使い分け
エアコンをより効率よく使いたいときは、送風モードを上手に取り入れるのがポイントです。
部屋がしっかり冷えた後や湿度が下がった後に送風モードへ切り替えると、エアコンの負担を減らしながら快適な空気環境を保つことができます。
さらに、扇風機やサーキュレーターを併用するのもおすすめです。
これらを組み合わせることで、エアコンの冷気や乾いた空気を部屋全体にまんべんなく届けることができ、冷房や除湿の効率アップにもつながります。
ただし、送風モードには温度調節や除湿の機能はないため、気温が高い日や湿度が気になるときには、冷房・除湿モードとの切り替えが必要です。
状況に応じて各モードを使い分けることで、無理なく節電が可能になります。
最近では、電力会社や家電メーカーの公式サイトでも、こうした使い分けのコツが紹介されているので参考にしてみるのも良いでしょう。
エアコン送風で湿度が上がるに関するまとめ
エアコンの送風モードを使っていると、「なんだか湿度が上がってきた気がする…」と感じることはありませんか?
実はそれ、エアコン自体が湿気を増やしているわけではないのですが、いくつかの理由で湿度が高くなることがあります。
例えば、冷房や除湿のあとに送風モードへ切り替えると、エアコン内部に残った結露水が風で室内に運ばれてしまい、それが湿度を上げてしまう原因になることがあります。
この現象は「湿度戻り」や「湿気戻り」とも呼ばれ、冷房が一時的に止まるタイミング(サーモオフ)の時に起こりやすいです。
さらに、湿度計で表示される「相対湿度」は温度によっても変化します。
送風モードで室温が下がると、空気中の水分量が同じでも湿度の数値が上がることがあるため、エアコンの調子が悪いと感じてしまうこともあるかもしれません。
でも、こうした変化はエアコンの故障とは限らないので、落ち着いて原因を見極めることが大切です。
湿度戻りを防ぐには、冷房の設定温度を少し低めにしてエアコンが頻繁に止まらないようにしたり、使用後に「内部クリーン」や「送風運転」を活用して中をしっかり乾かすのがポイントです。
また、フィルターの掃除など日ごろのメンテナンスも忘れずに行いたいですね。
エアコンの湿度管理は、仕組みを知ってうまく付き合うことがカギです。
もし気になる症状が続くようであれば、メーカーのサポートや専門の業者に相談してみるのも安心につながります。
快適な空間づくりのために、まずはエアコンの設定や使い方をもう一度見直してみてください。
▼その他の梅雨の湿度対策に関する記事はこちらをチェック▼
梅雨の湿度対策で快適な部屋づくり!部屋干しも安心のカビや臭いを防ぐテクニックまとめ

